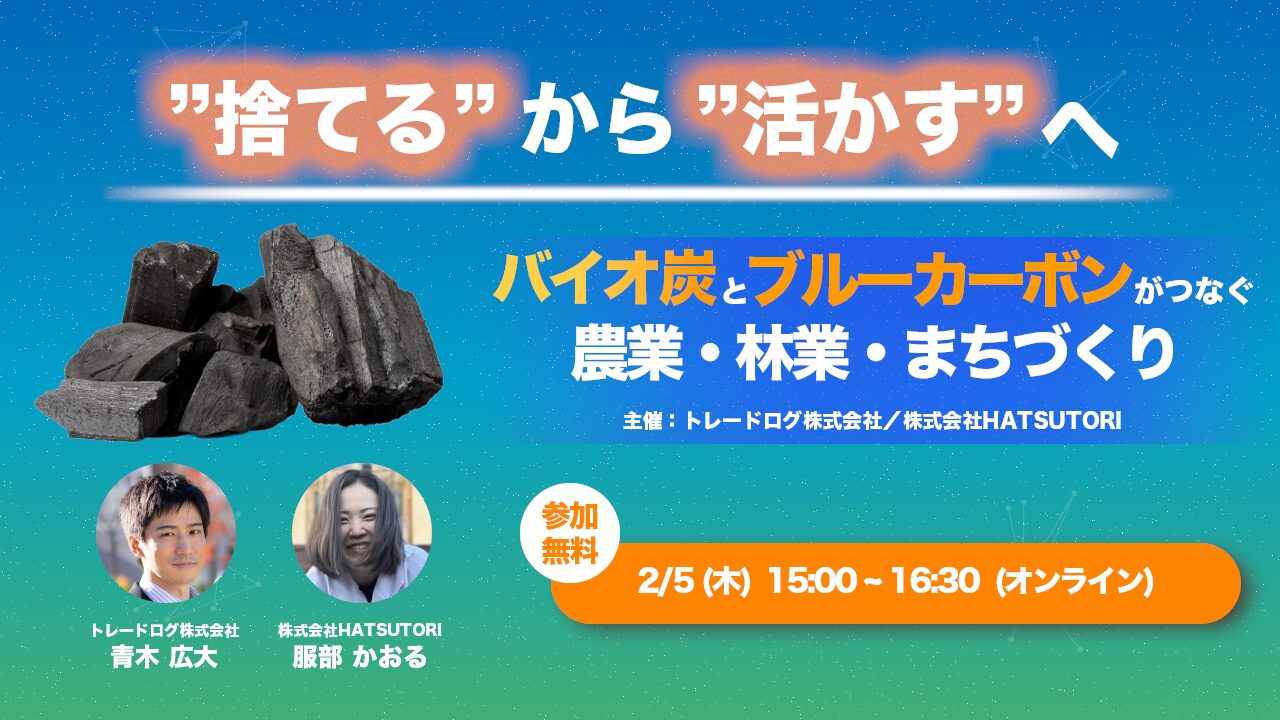自動車業界は今、大きな変革の時代を迎えています。電動化や自動運転技術の進展、サプライチェーンのデジタル化、さらには脱炭素社会に向けた規制強化など、多くの企業が新たな課題と向き合わなければなりません。こうした変化の中で、信頼性が高く透明性のあるデータ管理が求められる場面が増えており、その解決策として「ブロックチェーン技術」が注目されています。
ブロックチェーンは、金融分野だけでなく、サプライチェーン管理やモビリティサービスなど、自動車業界の幅広い領域で活用が進んでいます。例えば、バッテリーパスポートによるEV(電気自動車)バッテリーのトレーサビリティ向上、中古車市場における走行距離や修理履歴の改ざん防止、サプライチェーン全体の透明性強化など、具体的な導入事例が増えてきました。
本記事では、自動車・モビリティ業界におけるブロックチェーンの活用事例を詳しく解説し、企業がどのようにこの技術を導入できるのかを紹介します。ブロックチェーンの導入を検討する企業にとって、技術的な課題や導入メリットを理解することは重要です。ぜひ、自社のビジネスに活かすヒントを見つけてください。
そもそもブロックチェーンとは?
ブロックチェーンは、サトシ・ナカモトと名乗る人物が2008年に発表した暗号資産「ビットコイン」の中核技術として誕生しました。ブロックチェーンの定義には様々なものがありますが、噛み砕いていうと、「取引データを暗号技術によってブロックという単位にまとめ、それらを鎖のようにつなげることで正確な取引履歴を維持する技術」です。
一般的なデータベースとは異なり、中央管理者が存在せず、ネットワークに参加する複数のコンピュータ(ノード)が対等な立場でデータを管理する「P2P型(ピア・ツー・ピア)」の仕組みを採用しています。
従来のクライアントサーバ型のデータベースでは、一つの中央サーバーがデータを管理しますが、これには「単一障害点(SPOF:Single Point of Failure)」というリスクがあり、サーバーが攻撃や故障により停止すると、システム全体が機能しなくなる可能性があります。一方、ブロックチェーンではすべてのノードが同じデータを保持するため、一部のノードがダウンしてもネットワーク全体の運用に影響を与えません。
また、ブロックチェーンのデータはその名前の通り、一定量の取引情報を1つの「ブロック」にまとめ、それを時系列順に「チェーン」のようにつなげていくことで管理されます。このブロックをつなぐ際に使われるのが「ハッシュ値」と呼ばれる識別子です。
ハッシュ値とは、あるデータを入力すると一意の値が出力される数値のことで、「あるデータを何度ハッシュ化しても同じハッシュ値しか得られず、少しでもデータが変われば、それまでにあった値とは異なるハッシュ値が生成される」という特徴を持ちます。これにより、過去のデータが変更された場合、そのブロック以降のハッシュ値がすべて変わってしまうため、不正を検知しやすくなっています。
さらに、新たなブロックを生成するには、ある特定の条件を満たすハッシュ値を導く必要があります。ブロックの生成者は変数(=ナンス)を変化させながら、ブロックのハッシュ値を計算していき、最初に条件を満たすハッシュ値を見つけた作業者が、そのブロックの追加権を得て、報酬として新しい暗号資産を獲得する仕組み(ビットコインの場合)です。
しかし、この一連のプロセス(=マイニング)には膨大な計算リソースが必要であり、データを書き換えたり削除するのには、強力なマシンパワーやそれを支える電力が必要となるため、現実的には改ざんがとても難しいシステムとなっています。
このような特性を持つブロックチェーンは、金融分野だけでなく、サプライチェーン管理やカーボンクレジット取引など、データの透明性と信頼性が求められる分野で幅広く活用されています。次のセクションでは、ブロックチェーンがどのように利用されているのか、具体的な事例を紹介していきます。
なお、ブロックチェーンについては下記の記事で詳しく解説しています。
自動車・モビリティ業界のブロックチェーン導入事例7選
ブロックチェーンの基本を押さえたところで、ここからは自動車業界における具体的な導入事例を見ていきましょう。サプライチェーンの可視化や中古車取引の信頼性向上など、さまざまな用途で活用が進んでいます。それぞれの事例について、どのような課題を解決し、どんなメリットをもたらしているのかを詳しく解説します。
日産自動車:Web3で拓く新たなカーライフ体験「NISSAN PASSPORT BETA」
日産自動車は、自動車業界におけるデジタル変革を加速させる新たな試みとして、「NISSAN PASSPORT BETA」を2025年1月から開始しています。これは、テクノロジーの進化により、消費者のニーズが多様化し、デジタルとリアルをシームレスに融合させたサービスが求められる中で、透明性の高さを特徴とするブロックチェーン技術を活用してユーザー自身がデータやデジタル資産を安全かつ自由に管理できる、新たなデジタル体験の創出を目的としたプロジェクトです。
特に注目すべき取り組みが、限定5,523枚のメンバーシップNFTの発行です。NFTとは、ブロックチェーンを活用してデジタルデータの所有権を証明する技術のことで、本プロジェクトでは日産が提供するさまざまなサービスへのアクセスを可能にする「デジタル証明書」として機能します。
ユーザーは、自身の興味や嗜好に応じて「FUTURISTIC」「PERFORMANCE」「CLASSIC」「SMART LIFE」の4つのタイプからNFTを選択し、日々の行動に応じてこれらのNFTが進化していくという育成ゲームのようなユニークな要素も面白そうです。
また、通常はNFTの管理には「ウォレット」と呼ばれる管理ツールが必要ですが、同社ではWeb3(ブロックチェーンなどの技術によって実現される次世代の分散型インターネット)に不慣れなユーザーでも安心して利用できるよう、独自のWeb3ウォレットを提供しています。このウォレットは専用の口座開設や手数料が不要で、直感的な操作性を備えたスマートフォンアプリのような使い勝手を実現しており、高度なセキュリティ対策も施されています。
さらに、日産とユーザー、さらにはユーザー同士が直接つながる場として、Discordを活用したコミュニティも開設されます。このコミュニティでは、日産車の写真投稿や旅先での思い出の共有、さらにはユーザー主導で新しいサービスや体験を企画することも可能です。活動や貢献度に応じて特別なデジタルバッジが付与される仕組みも実装されるとのことで、「ポケモンGO」のように日々の生活の一部として楽しむユーザーも出てくるかもしれませんね。
従来、自動車メーカーと顧客の関係は「販売」と「購入」にとどまるものでしたが、日産はこのプロジェクトを通じて単なる商品提供にとどまらず、ユーザーとの継続的な関係を築くことを目指しています。今回の取り組みはまだ試験的な段階ですが、特別な試乗体験や限定車の試乗権が報酬となる体験型リワードプログラムなども計画中とのこと。デジタル時代の新たなカーライフパートナーとして活躍する同社の動向には今後も要注目です。
ボルボ・カーズ:EVの持続可能な普及を目指す「バッテリーパスポート」
ボルボ・カーズは、ブロックチェーンを活用した世界初のバッテリーパスポートを導入した企業として知られています。バッテリーパスポートとは、自動車等のバッテリーに関する情報を詳細に記録し、透明性を確保するためのデジタル証明書のようなもので、バッテリーの原材料の原産地、製造工程、カーボンフットプリント、リサイクル率などがデータとして残るため、消費者は環境負荷を考慮した選択ができるようになるというメリットがあります。
ボルボの次世代SUV「EX90」シリーズでのバッテリーパスポート対応を機に導入が本格化し、2025年発売予定の新型セダン「ES90」にもこのシステムが採用される予定です。同シリーズは、ボルボ初の800V電気システムを搭載しており、フル充電で700kmの航続距離を確保できる脅威の高性能EVとして市場を賑わせていますが、リチウムやコバルトなどの原材料の調達元を可視化することで、持続可能な調達を望むエシカルな消費者のニーズにも対応しています。
同社のバッテリーパスポートは英国の新興企業Circulorとの協力のもと、ブロックチェーン技術を活用して構築されており、消費者向けの簡易版と、規制当局と共有される詳細版の2種類があります。オーナーは、運転席ドアの内側にあるQRコードをスキャンするだけで、バッテリーの情報を簡単に確認できる仕組みで、詳細版はバッテリーの15年間の健康状態を追跡し、中古EVの価値判断にも役立つ情報が含まれているそうです。
実は、こうした取り組みは単なる自主的な活動という訳ではありません。EUでは2027年2月から、域内で販売されるすべてのEVにバッテリーパスポートの搭載が義務付けられています。このバッテリーパスポートの導入には、サプライヤーの生産システムと統合し、すべての材料の流れを正確に追跡する必要があるため、多くの自動車メーカーがこの期限に間に合わせるのに苦労しているのが実情です。
そのような状況下で、ボルボはブロックチェーンを活用することでバッテリーの原産地やカーボンフットプリント(製造・使用に伴うCO2排出量)を正確に記録し、サプライチェーンの透明性を確保しているということは特筆すべき事項です。消費者がより信頼できる情報をもとにEVを選択できる環境を整え、持続可能な社会の実現に貢献することを目指す、という点で、この事例もブロックチェーンの活用意義を大きく広げる好例といえるでしょう。
アルファ ロメオ:「Tonale」に導入されたNFT技術がもたらす新たな信頼性

アルファ ロメオは、コンパクトSUV「Tonale(トナーレ)」にNFT技術を活用したデジタル認証機能を導入しました。これは、自動車業界において初めての試みであり、従来の車両履歴管理の概念を大きく変える可能性を秘めています。
従来のデジタルデータはコピーや改ざんのリスクがありましたが、NFTを活用することで、車両の履歴情報を不正なく安全に管理できるようになります。トナーレのオーナーは、専用のスマートフォンアプリ「My Alfa Connect」から車両情報を入力し、タイムスタンプ付きのNFT証明書を発行できます。証明書には、日付、ブランド名、モデル名、車体番号(VINナンバー)、走行距離といった基本情報が記載されており、将来的には追加項目も予定されています。
このNFT証明書は、特に中古車市場においてその真価を発揮します。従来の車両履歴の証明は、整備記録や売買契約書に依存していましたが、これらの書類は紛失や改ざんのリスクが伴いました。しかし、NFT証明書はブロックチェーン上に記録されるため、所有者やディーラーによる改ざんは不可能であり、信頼性の高い車両履歴を証明するツールとして機能します。したがって、中古車購入時の安心感が高まり、適正な価値評価が期待できるという訳です。
また、車両の信頼性向上により、オーナーにとっては残存価値が向上するメリットもあります。従来は、走行距離や整備履歴の不透明さが中古車の価値を左右する要因となっていましたが、NFT技術の導入によって透明性が確保され、正当な評価が行われるようになります。この点は、特に長期的に車両を所有するユーザーにとって大きなメリットと言えるでしょう。
同社のこの取り組みは、自動車業界におけるNFT活用の可能性を示す先駆けとなる事例です。今後、ブロックチェーン技術がさらに進化することで、車両履歴管理だけでなく、保険契約やリース契約など、多岐にわたる分野での活用が期待されます。デジタル技術と自動車の融合による新たな価値創造に、今後も注目が集まることでしょう。
米カリフォルニア州自動車局(DMV):「アバランチ(Avalanche)」で変わる車両所有権の管理

米カリフォルニア州自動車局(DMV)は、ブロックチェーン技術を活用し、自動車の所有権登録をデジタル化する革新的なプロジェクトを進めています。これまで車両の所有権移転には、書類のやり取りや窓口での対面手続きが必要でしたが、こうした煩雑さを解消し、よりスムーズで安全な仕組みを構築しようとしています。
この取り組みは、テクノロジー企業オックスヘッド・アルファ(Oxhead Alpha)と、レイヤー1ブロックチェーン「アバランチ(Avalanche)」の協力によって実現しました。現在、カリフォルニア州で登録されている4,200万台もの車両情報がブロックチェーン上に記録されており、今後はスマートフォンの専用アプリを通じて、簡単に所有権を管理できるようになる予定です。
この車両管理のデジタル化によって多くのメリットが生まれます。例えば、従来であればDMVの窓口に出向き、書類を提出し、数週間待たなければならなかった名義変更手続きが、モバイルウォレットを使って数分で完了するようになります。また、ブロックチェーンの特性を活かすことで、不正行為のリスクが大幅に軽減されるのも大きな利点です。特に、自動車の所有権を担保にした詐欺を防ぐ効果が期待されています。
さらに、このプロジェクトは所有権管理の効率化にとどまりません。バンク・オブ・アメリカの調査によると、NFT技術を活用すれば、車両の所有権を細分化し、分散型金融(DeFi)を通じた新たな流動性の創出が可能になるといいます。将来的には車をNFT化し、それを担保に融資を受けるといった未来もありえるかもしれないですね。また、スマートコントラクトと呼ばれる契約自動化の仕組みを利用したエスクローシステムを導入すれば、安全かつスピーディーな取引も実現できるはずです。
カリフォルニア州は、Web3技術の規制整備を進めると同時に、行政サービスへのブロックチェーン活用を推進しています。DMVのプロジェクトもその一環であり、今後の成功次第では、他の州や国の行政機関へと広がる可能性も十分にあるでしょう。
トヨタ自動車:車両の所有権・使用権の概念を変える「スマートアカウント」

トヨタ自動車は、ブロックチェーン技術を活用し、次世代のモビリティ社会を実現する取り組みを進めており、同社の研究開発組織「トヨタ・ブロックチェーン・ラボ(TBL)」は、イーサリアム・ブロックチェーンを基盤とした「スマートアカウント」を導入し、車両のデジタル管理を革新しようとしています。
この構想の核となるのは、車両に関する権利をブロックチェーン上でトークン化し、「MOA(モビリティ指向アカウント)」として管理する仕組みです。MOAを導入することで、車両は単なる移動手段にとどまらず、プログラム可能な「サービス」として機能し、他のデジタルサービスと柔軟に連携できるようになります。さらに、将来的には完全自動運転を視野に入れ、車が独立した経済主体として運用される可能性もあります。
「トークン化なんて前から出来たんじゃないの?」と思う方もいるかもしれませんが、従来までの車両に関するデジタルアカウントを作成する方法は、外部所有アカウント(EOA)と呼ばれ、ユーザーが秘密鍵を用いて管理するものでした(仮想通貨の世界では、ウォレットを使って他者へコインを送金していますが、このウォレットに紐づくアカウントがEOAです)。つまり、紛失時にアカウントを復旧できないリスクがあったのです。
そこでTBLは、この課題を解決するため、イーサリアムの「アカウント抽象化(ERC-4337)」を活用したMOAを提案。秘密鍵の管理と認証プロセスを分離することで、鍵を紛失してもアカウントを維持できる仕組みを構築しました。また、一対一で対応する秘密鍵を有していないMOAでは、スマートコントラクトを活用し、車両の権利管理をより柔軟に実現します。例えば、カーシェアリングの利用者が事前に決められた時間内で車を使用できるように設定し、時間が過ぎれば自動的に権利が回収されるような仕組みも構築できるでしょう。
また、MOAのシステムの下では「キー・トークン・コントラクト(Key Token Contract)」と呼ばれる車両の使用権をトークン化したもの(ERC-721に準拠しているとのことなのでNFTと推測されます)を導入することで、従来の車両キーのように物理的な制約に縛られることなく、特定の機能に限定したアクセス権を発行することができます。配送業者にトランクでの開閉権限だけを発行して「置き配」サービスの受け取りをよりセキュアな環境で行う、といったこともできるとしたら、個人的にはとてもありがたいですね。
ブロックチェーン技術を活用することで、車両の所有や使用権の管理がよりシンプルで安全になり、新たなモビリティサービスの創出が可能になります。トヨタの挑戦は、単に技術革新を進めるだけでなく、未来の移動のあり方を根本から変える可能性を秘めているのです。
KINTO:譲渡不可能なSBTが実現する新たな安全運転評価のカタチ
モビリティ業界において、サブスクリプション型のカーリースを提供するKINTOは、安全運転ドライバーを証明するNFTを発行してブロックチェーン上に記録することで、モビリティサービスの新たな価値創出を目指しています。
これまでの自動車業界では、運転の質を正確に評価し、それをドライバーのメリットにつなげる仕組みが十分に整っているとはいえませんでした。保険会社やレンタカー業者が運転履歴を考慮することはありましたが、体系的に評価される場は限定的で、ドライバー個人が自身の安全運転の証明を活用できる機会は少なかったのです。
しかし、KINTOの新たな試みでは、トヨタ自動車の「コネクティッドドライブトレーナー」という運転分析機能によって収集された運転データを分析し、アクセルやブレーキの操作、ハンドルの切り方など5つの安全項目をもとに「安全運転」と認定されたドライバーに対して、譲渡不可のNFTである「Soulbound Token(SBT)」を発行することで、ブロックチェーン上にその証明を残します。
ブロックチェーン上の改ざんが困難な環境で記録された運転履歴により、ドライバー自身の日々の心がけが正しく評価されるだけでなく、モビリティ関連サービスにおいてそうした優良ドライバーへ特典を付与できる可能性を模索しているといった具合でしょうか。ユーザー目線では、自動車保険の割引や、企業の社用車利用時の評価基準などが活用先となると嬉しいですね。
このように、ブロックチェーン技術の活用によって運転技術が適正に評価されることで、ドライバーの安全意識の向上にもつながるでしょう。実証実験から本格的なサービスに至った際には、KINTOに限らず他の自動車メーカーやモビリティサービス企業も追随し、ドライバーの運転履歴がより透明に、そして公正に評価される時代が訪れるかもしれません。
アントチェーン:従来のリサイクル方法からの脱却と二次流通市場の透明化
中国のアントグループ傘下のテックブランド「アントチェーン」は、電動バイク向けバッテリー交換プラットフォーム「嘟嘟換電(Duduhuandian)」との提携を通じて、4000カ所以上の交換ステーションにおいて数万個のバッテリーにブロックチェーン技術を導入し、最新鋭のバッテリー管理システム(BMS)を構築しています。
この技術の最大の利点は、リサイクル企業が廃電池の状態をオンラインで確認できる点にあります。従来のリサイクル方法では、バッテリーを分解して手動で健全度をチェックしていましたが、この過程は時間とコストがかかり、また精度にも限界がありました。しかし、ブロックチェーンの導入によって、リサイクル企業は各電池セルの電力量や充放電回数、健全度といった正確なデータをリアルタイムで確認できるため、検査のコストを大幅に削減できるようになります。
この技術をうまく応用すれば、効率的なカスケード利用(繰り返し利用されて品質が下がったエネルギーを別のシーンでうまく再利用すること)も可能です。例えば、リチウムイオン電池の寿命が80%以下に低下すると、EVとして再利用することは難しくなってしまうのですが、電力消費の少ない低速電動車や家庭用蓄電池としては、まだまだ活躍のチャンスがあります。
とはいえ、古着や中古物件に抵抗感がある人が一定数存在するように、中古のバッテリーには不信感を抱く消費者が出てきてもおかしくないですよね。そこでブロックチェーンの耐改ざん性が生きてくるという訳です。実際、アントチェーンの導入事例では、健全度が高いバッテリーパックがリサイクル時に従来の3倍の価格で販売できるようになったといいます。つまり、この技術の導入は、単にリサイクルコストを削減するだけでなく、電池の価値を最大化し、サステナブルな経済活動を支える大きな一歩となっているのです。
新エネルギー車の市場拡大が著しい中国では、近い将来、EVバッテリーが大量廃棄されるシナリオが迫っており、リサイクル業者はその対応に迫られています。この状況を前に、アントチェーンが展開するブロックチェーン活用の取り組みは、業界におけるゲームチェンジャーとなる可能性を秘めているといえるでしょう。
自動車・モビリティ業界にブロックチェーンを導入するメリット・必要性

自動車業界におけるブロックチェーン活用は、単なる技術革新ではなく、業界全体の競争力を高める重要な要素となりつつあります。特に、バッテリー管理の厳格化や中古車市場の透明性向上、新しいモビリティサービスの創出といった側面で、ブロックチェーン技術が果たす役割は大きいといえるでしょう。以下では、具体的なメリットを解説します。
バッテリーパスポートなど国際的な法規制に対応できる
EV(電気自動車)の普及が進む中、バッテリーの管理とリサイクルの透明性を確保するための国際的な規制が強化されています。その代表例が記事内でもご紹介した「バッテリーパスポート」です。これは、バッテリーの製造過程から廃棄・リサイクルに至るまでの情報を記録し、トレーサビリティを確保する仕組みですが、従来のデータ管理手法では改ざんリスクや情報の断絶といった課題が残ります。
ブロックチェーンを活用すれば、バッテリーの製造元や成分情報、充放電回数、リサイクル履歴などを改ざん不可能な形で記録し、信頼性の高いデータ管理が可能になります。これにより、自動車メーカーやバッテリー供給企業は規制遵守をスムーズに進めることができ、消費者も安心してEVを選択できる環境が整います。
中古車市場の信頼性を向上できる
中古車市場では、走行距離の改ざんや事故歴の隠蔽といった不正が長年の課題となっています。特に、グローバル市場においては国境を越えた取引が行われるため、信頼できるデータ管理が求められています。
「50万円必要です」 中古車業界にはびこる闇? 事故車や“起こし屋”の手口… 元ディーラーが語る「保証の落とし穴」とは(Merkmal) – Yahoo!ニュース
ブロックチェーンを活用することで、走行距離やメンテナンス履歴、所有者の変更履歴などを一元的かつ不正ができない形で管理できます。例えば、日本で使用されていた車両が海外へ輸出される際にも、過去のデータを正確に追跡できるため、買い手にとっての信頼性が向上し、適正な価格での取引が可能になります。結果として、中古車市場全体の健全化が進み、業界全体の価値向上につながるでしょう。
新しいサービスを創出できる
ブロックチェーン技術は、単なるデータ管理の枠を超え、モビリティサービスに革新をもたらす可能性を秘めています。MaaS(Mobility as a Service)との連携によって、個人の移動データを安全に管理し、多様な交通手段を統合することで、よりスムーズな移動体験が期待できます。
スマートコントラクトの活用も、カーシェアリングやサブスクリプションサービスの効率化に貢献します。利用時間に応じた料金を自動で精算する仕組みは、契約の透明性を高め、ユーザーの利便性を向上させるでしょう。
加えて、NFT(Non-Fungible Token)の導入は、モビリティ分野に新たな顧客体験をもたらすと考えられます。特定の移動手段の利用権やイベントへのアクセス権などをNFTとして発行することで、これまでにないユニークな体験を提供できる可能性があります。地域限定のNFTは、観光客の誘致や地域活性化にもつながるかもしれません。
このように、ブロックチェーン技術は、効率化や利便性の向上に加え、NFTを活用した新しい顧客体験の創出を通じて、モビリティサービスの未来を大きく変える可能性を秘めているといえるでしょう。
自動車業界にブロックチェーンを導入する上での課題

ブロックチェーンは、自動車業界に多くのメリットをもたらしますが、導入にはいくつかの課題も存在します。技術の特性上、データ管理や人材確保、運用コストといった面での障壁があり、これらを乗り越えることが求められます。
法規制対応のための情報量が不足している
ブロックチェーンを活用する領域で、法規制対応は避けて通れない課題です。特に自動車業界においては、前述の「バッテリーパスポート(Battery Passport)」をはじめ、各国でサプライチェーン透明化や環境規制の強化が急速に進んでいます。しかし、日本国内ではこれらに関する情報が十分に流通していないのが実情です。
例えば、バッテリーパスポートに関しては、EUが独自に法制化を進めており、内容やスケジュールも頻繁にアップデートされています。しかし、その詳細について、政府や公的機関が日本語で体系的に解説してくれる場はほとんどなく、多くの日本企業は、英文で公開される膨大な規制文書や関連資料を自力で読み解き、情報をキャッチアップせざるを得ません。さらに、どのようなデータを、どの形式で、どこまで準備すべきかについての具体的なガイドラインも、現状では十分に整理されていません。
この傾向は、バッテリー分野に限らず、今後適用が予定されている「デジタル製品パスポート(DPP: Digital Product Passport)」においても同様です。DPPは、自動車だけでなく、電子機器や繊維など広範な製品分野に拡大される見込みですが、その内容も欧州中心に議論・設計が進んでおり、日本企業は最新情報の取得や対応に苦慮しています。結果として、規制対応におけるブロックチェーン活用の議論も、十分な情報基盤がないまま進めざるを得ないという、歪な構造が生まれています。
ブロックチェーンエンジニアが不足している
ブロックチェーンの活用には、スマートコントラクトの開発やノード管理、ネットワークの最適化など、高度な専門知識が求められます。しかし、現在の市場ではブロックチェーン技術を熟知したエンジニアが不足しており、導入を検討している企業にとって大きなハードルとなっています。
特に、自動車業界はブロックチェーン開発の経験が浅い企業も多いため、社内でブロックチェーン人材を育成するのか、それとも外部の専門企業と協業するのかという戦略的な判断が求められます。人材確保のためには、ブロックチェーン技術者向けの研修プログラムの充実や、業界内でのノウハウ共有が重要になるでしょう。
ブロックチェーンを稼働させるためのコストが発生する
ブロックチェーンの導入には、ノードの運用コストやネットワーク維持費、システム統合のための開発費用など、一定のコストが発生します。特に、パブリックチェーンを利用する場合は、トランザクション手数料(ガス代)も考慮しなければなりません。
一方で、プライベートブロックチェーンを採用すれば、コストは抑えられるものの、ネットワークの分散性が低下する可能性があります。このように、導入目的やシステム要件に応じた適切な設計が必要です。企業がブロックチェーンを採用する際には、ROI(投資対効果)を明確にし、長期的な視点でのコスト管理を行うことが重要になります。
自動車業界へのブロックチェーン導入は当社にお任せください!
自動車業界におけるブロックチェーン活用は、今後ますます重要性を増していくことが予想されます。しかし、その導入には法規制対応やエンジニア不足、コストといった課題も伴います。
当社は、ブロックチェーン技術を活用したシステム開発に豊富な実績を持ち、自動車業界におけるさまざまなユースケースに対応しています。世界のモビリティ産業に対して精緻なエコシステムを主導するコンソーシアムであるMOBIにも参画しており、最新の法規制動向にも精通しております。
トレードログが参画しているMOBI主導のグローバルバッテリーパスポートシステム(GBPS)の構想初年度が完了しました|PR TIMES
貴社の課題に合わせた最適なブロックチェーンソリューションを提案し、導入から運用までしっかりとサポートいたします。ぜひ、お気軽にご相談ください。
-1.png)