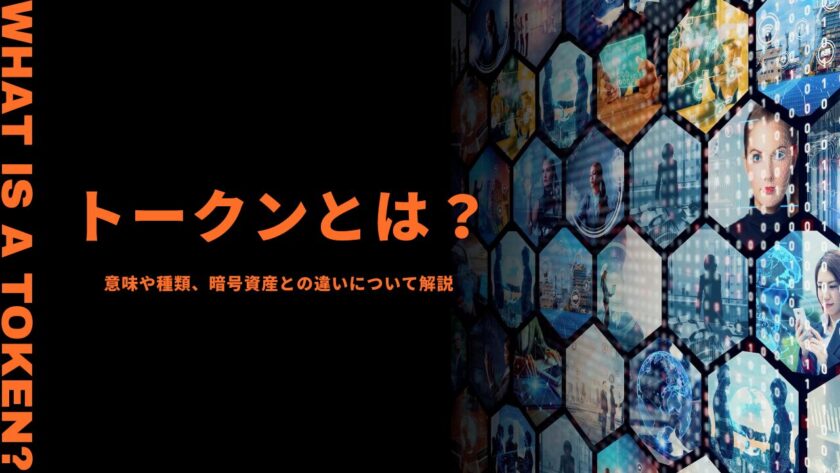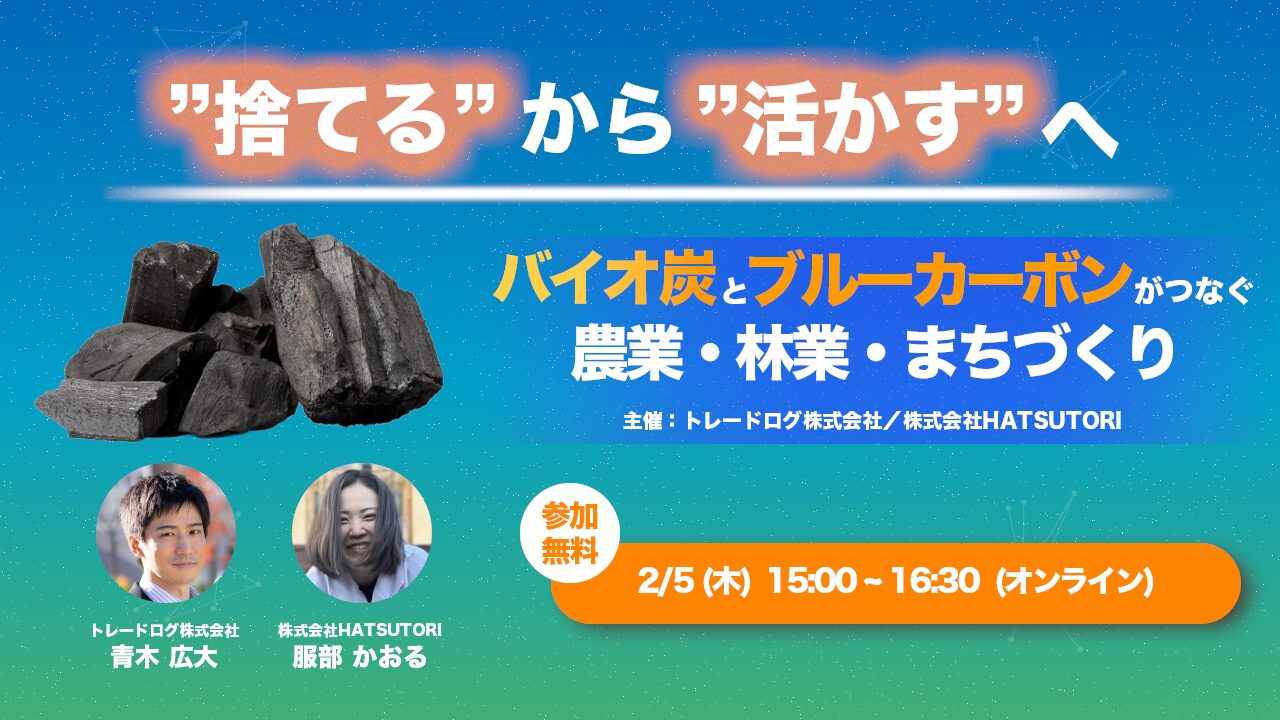暗号資産(仮想通貨)に関連してよく耳にする言葉に「トークン」があります。トークンという言葉自体は暗号資産やWeb3.0の世界以外でも使われており、様々な意味合いを持っています。しかし、改めてトークンとはなにかを説明しようとするとうまく言葉で整理できない人も多いようです。
今回は「トークンとはそもそも何なのか?」をテーマに、その定義から注意点、混合しやすいキーワードとの違いや複雑な分類まで一気に解説します。ぜひ最後までご覧ください。
トークンとは?

トークン=取引の証拠
まずはトークン(token)の言語的な意味から紐解いていきましょう。語源辞典であるEtymonlineによると、トークンは本来、「証拠」「印」を意味する単語でした。しかし、これは具体的には何を指し示す「証拠」のことなのでしょうか?
トークンが生まれたとされる紀元前8,000年頃よりもさらに前の紀元前9,000年頃、人類は大きな転換期を迎えます。定住せずに狩りや採集といった行動によって食料を得て「その日食べられるだけ食べる」という獲得経済から、農耕や牧畜を主とする生産経済への移行を始めたのです。
食料がある程度備蓄できるようになると、人々は牛などの家畜を通貨の代わりとして使い出すようになります。しかし、こうした家畜は通貨として持ち運ぶにはとても不便ですし、死んでしまうと資産価値がゼロになってしまいます。
そこでメソポタミア文明では、円盤状をした小さな粘土の塊に取引内容を記録して生活を営むことにしました。この小さな粘土から作られた小さな陶器が最古のトークンといわれています。記録したい取引の内容に呼応したトークンを所持することで、食料などのアイテムを実質いくつ所持しているのかを可視化できるという仕組みです。
▼トークン研究第一人者であるデニス・シュマント=ベッセラ(Denise Schmandt-Besserat)の著書『How writing came about』の表紙には、世界最古のトークンが描かれている。(出典:University of Texas Press)
つまり、トークンとは「取引の証拠」として発達してきた存在だといえます。その過程で貨幣や紙幣が誕生し、モノが金銭によって取引されるようになると、今度は商品券や映画・イベントの入場チケット、カジノのチップやパチンコ玉など、前払いの証明や流通性・利便性の向上のために様々なシーンでトークンが使用されるようになります。
現代ではトークンという言葉が、プログラミング分野(「最小単位」という意味のトークン)やITセキュリティ分野(「ワンタイムパスワード」としての認証トークン)などでも使用されるようになり、その都度、「トークン」という言葉が表す意味は異なってきます。原義のニュアンスを踏まえつつも、個別のサービスに応じた柔軟な解釈が必要でしょう。
暗号資産(仮想通貨)の世界におけるトークン
暗号資産の世界では、既存のブロックチェーンプラットフォームを利用して新たに発行された暗号資産のことをトークンと呼びます(反対に、既存のブロックチェーンプラットフォーム固有の主軸通貨は「ネイティブトークン」「ネイティブコイン」と呼ばれます)。これらは、ビットコインやイーサリアムといった「親」となるブロックチェーンのシステムを間借りして発行されており、独自の専用チェーンを持ちません。いわば、スーパーやコンビニが独自に発行しているポイントに近いものです。
こうしたトークン自体は自由に売買することができ、決済に使用するだけでなく現実世界の資産やゲーム内の仮想アイテムなど、多くの実用性を兼ね備えています。ここ最近、「トークン」という言葉をよく耳にするようになった背景としては、この暗号資産やブロックチェーンの存在が大きな要因といえるでしょう。
しかし、物理的に現実世界に存在するトークンは第三者による改ざんが重大な弱点であり、コピーガードやOPニス、擬似エンポスといった対策が取られてきたものの、物理的な形を要するギフトカード等は偽造品による被害が収まることはなく、その公平性が保たれにくいという課題がありました。
一方、耐改ざん性や透明性といった性質を兼ね備えるブロックチェーン技術によって発行されたトークンではこういった不正行為は極めて困難であり、活用用途も幅広いものとなっています。ブロックチェーンについては以下の記事で詳しく解説しています。
コインとトークンは何が違う?
トークンとよく混同される言葉に「コイン」があります。コインとトークンは一般的には、どちらも暗号資産という言葉でまとめられることが多いですが、実際には両者の間には明確な違いがあります。 ここでは、この2つの概念を少し掘り下げて解説します。
前述の通り、トークンとは既存の暗号資産プラットフォームを間借りする形で発行された暗号資産を指します。一方で、コインは専用のブロックチェーンを使って発行された、そのプラットフォーム固有の主軸通貨を指します。代表的な仮想通貨であるビットコイン(BTC)とイーサリアム(ETH)は、それぞれ独自のブロックチェーンを使って発行されています。コインはトークンと比較して「ネイティブトークン」とも呼ばれます。
コインとトークンの大きな違いは、コインがカレンシータイプの暗号資産であることに対し、トークンはアセットタイプの暗号資産であるという点です。カレンシータイプであるコインは、発行者が存在せず、上限枚数が存在します。発行数にキャパシティが設けられているということは、コインが市場に出回り過ぎて希少価値が薄れる可能性も低く、価値が安定しているということです。
こうした側面から暗号資産は別名の「仮想通貨」の名の通り、インターネット上のボーダーレスな法定通貨として人気を博することになります。特定の国家や銀行に依存しない上に、従来の国際送金と比べても迅速かつ低コストで「いつでも」「どこでも」「だれでも」自由に送金できる仕組みがコインの特徴です。
対してトークンは、あるアプリケーションの中で決済に使用されたり、特定の権利を代替したり、消費を目的としたりなど、エコシステムに実用性を与える存在です。コインとは異なり、トークンは単に価値の保有や交換だけでなく、分散型議決権、NFTのようなデジタル収集品、あるいは米ドルのような現実世界の資産をブロックチェーンベースで表現するなど、幅広い用途で利用されています。
また、コインはそれぞれ独立したチェーンを持っているが故に取引所を通じてコイン同士を交換する必要がありますが、トークンは同じエコシステムのチェーンであればUniswap(ユニスワップ)などのDEX(分散型取引所)を通じて簡単に交換することができます。実際に、Ethereumを利用して運用されているブロックチェーンでは、数あるERC-20トークンや多くのNFTがサポートされています。
トークンの様々な種類
暗号資産の世界におけるトークンには、その目的によって様々な呼称がついています。ここからは、数あるトークンの種類とその特徴について簡単に説明していきます。
ただし、すべてのトークンが定義通りの役割を持っていたり、どれか一つの種類だけに分類されるわけではなく、文脈や状況に応じてトークンという言葉が意味するものが異なる場合があるので、その点は注意しましょう。
RWA(Real World Asset)トークン
RWA(Real World Asse)は日本語で「現実資産」と表現され、株式や債券、不動産、コモディティなどの現実世界に物理的に存在する資産のことを指します。RWAトークンとは、こうした現実資産をトークン化したものであり、資産をデジタル化することによって、売買を活発に行ったり、安全に取引ができるようになります。
RWAの紐づく対象は多岐にわたり、上記のようないかにも「資産」というイメージの強いものもあれば、トレーディングカードやスニーカー、ワインや日本酒といった従来では「コレクターズアイテム」に過ぎなかったものでもトークン化することが可能です。伝統的な金融システムでは取り扱うことが難しい投資対象であっても、トークンとして扱うことができる点は大きな利点でしょう。
また、RWAトークンは将来的な現実資産にも適用可能です。予約販売されるような商品やサービス利用権を事前に販売することで、企業側は事前にキャッシュを得ることができます。そのため、今後はRWAトークンを活用した資金調達や資金運用が活発になっていくのではないかと大きな注目を集めています。
ユーティリティトークン
ユーティリティトークンは、トークンそれ自体は金銭的価値をもたず、具体的な他のアセットと交換することによって初めて資産性が生まれるトークンです。
例えば、ロックミュージシャンのコンサートチケットもユーティリティトークンの一つです。というのも、このチケットが価値を持つのは、チケットを使うことで生の演奏を聞くことができると約束されているからです。したがって、コンサート開催日の翌日以降であったり、そのミュージシャンを知らない人間しかいない地域であったりすると、そのチケットには1円の価値もなくなります。
また、別の例で言えば、JRの切符を西武鉄道で使っても意味がないのと同じ話です。このようにユーティリティトークンは、他のアセットとの交換可能性を金銭的価値に変えられるトークンであることから、次のような特徴をもちます。
- 閉じられた(=一部の人間に限定された)コミュニティや地域などで効果を発揮しやすい
- トークン自体は物質的価値をもたなくてもよい
- 交換対象となるアセットの価値を定量化できる
こうした諸特徴は、既存のビジネスに活用するうえで非常に使い勝手が良いため、ユーティリティトークンはブロックチェーンの技術とともに様々な領域で活用され始めています。
また、RWAトークンとユーティリティトークンはしばし似たようなニュアンスを持ちますが、RWAトークンが現実の資産に紐づいて価値の裏付けがあるのに対して、ユーティリティトークンは、単にサービスやコミュニティへのアクセス権に過ぎず、価値の裏付けはありません。
セキュリティトークン
セキュリティートークン(ST)は、従来の有価証券をブロックチェーン技術を用いて電子化(トークン化)したものです。ここでの「セキュリティ」は一般的に使われる「安全性」という意味ではなく、「証券」という意味です。広義には先ほど紹介したRWAトークンの一つとされますが、特に、証券性を持つRWAトークンのことをセキュリティトークンと呼びます。
セキュリティトークンは有価証券と同様、資金調達の一環として発行されることが多いですが、ブロックチェーンを活用することにより、デジタル上でのデータの安全性を担保したうえで24時間いつでも取引が可能になっています。まさに、株式や社債、不動産の持分などをトークン化し、従来の証券市場と同等の法的枠組みの中で流動性を高めることが可能になるため、透明性と利便性を兼ね備えた新たな資金調達法といえるでしょう。
セキュリティトークンを利用した資金調達法では、法制面での整備も追いついています。セキュリティトークンは証券会社を通して購入することになりますが、発行企業も各国の金融商品取引法に準拠したトークンを発行する必要があるため、投資家も安心して投資をおこなうことが可能です。
コインを利用した資金調達法のICO(イニシャル・コイン・オファリング)ではスキャム(詐欺)が横行しましたが、セキュリティトークンを活用してクリーンな市場整備を進めているSTO(セキュリティ・トークン・オファリング)ではこうした問題は起こりにくい仕組みとなっています。
STOについては詳しくは以下の記事でも解説しています。
ガバナンストークン
ガバナンストークンとは、投票権のついているトークンのことです。トークンの保有者は、DAO(分散型自律組織)やDApps(分散型アプリ)などの開発・運営に関わる意思決定に参加することができます。つまり、これら分散的なシステムにおける運営方針はガバナンストークンのホルダーによって決まるということです。
従来型のガバナンスモデルでは、原則的にはトップダウン方式を採用し、個々のメンバーの考え方が一致しなかったとしても、十分な報酬を支払って雇用関係を維持することで組織運営を継続していきます。
一方、分散型のガバナンスモデルでは特定の主体がプロジェクトの意思決定権を持ちません。ガバナンストークン保有量に準じ、一種の「民主主義」としてプロジェクトの意思決定を行うことにより、常にメンバーたちにとっての最適解を導き出すことができます。
結果として、プロジェクトに対して熱意のあるメンバーはより多くのガバナンストークンを取得することで発言権を増やすこともでき、こうした循環によりコミュニティの結束力が向上するという仕組みです。
また、ガバナンストークンはプロジェクトに必要となる資金調達としての役割を兼ねていることもあります。発行上限が設定されているガバナンストークンは一定の希少性を持つため、多くのガバナンストークンが発行上限を設定しています。
とはいえ、セキュリティトークンのように資金調達を全面に出しているわけではなく、主目的はあくまでガバナンスです。そのため、プロジェクトによっては保有インセンティブを設けるなどして、保有者に長期保有を促しているものもあります。
NFT
NFT(Non-Fungible Token)とは、代替不可能なトークンのことです。ブロックチェーン技術を採用することで、見た目だけではコピーされてしまう可能性のあるコンテンツに固有の価値を保証しており、現在ではアートやブロックチェーンゲームにおいて主に活用されています。
簡単にいうと、NFTとは、耐改ざん性に優れた「ブロックチェーン」をデータ基盤にして作成された、唯一無二のデジタルデータのことを指します。イメージとしては、デジタルコンテンツにユニークな価値を保証している「証明書」が付属しているようなものです。
不動産や宝石、絵画などPhysical(物理的)なものは、証明書や鑑定書によって「唯一無二であることの証明」ができます。しかし、画像や動画などのDigital(デジタル)な情報は、ディスプレイに表示されているデータ自体はただの信号に過ぎないため、誰でもコピーできてしまいます。
そのため、デジタルコンテンツは「替えが効くもの」と認識されがちで、その価値を証明することが難しいという問題がありました。実際、インターネットの普及によって音楽や画像・動画のコピーが出回り、所有者が不特定多数になった結果、本来であれば価値あるものが正当に評価されにくくなってしまっています。
NFTではそれぞれのNFTに対して識別可能な様々な情報が記録されています。そのため、そういったデジタル領域においても、本物と偽物を区別することができ、唯一性や希少性を担保できます。これまではできなかったデジタル作品の楽しみ方やビジネスが期待できるため、NFTはいま、さまざまな分野で実用化が進んでいます。
NFTについては詳しくは以下の記事でも解説しています。
SBT
SBT(Soul Bound Token)とは、前述のNFTの一種であり、NFTと同様に代替性を持たないトークンですが、譲渡が不可能かつ受け取った本人以外は利用ができないトークンを指します。
譲渡や売買ができないNFTであるため、トークンを投機目的で収集している人にとってはまったく意味のないNFTです。一方、SBTではNFTを応用したID系のソリューションと比較して、より強力に自身のアイデンティティや履歴を表現・証明可能です。
現在、SBTが最もマッチすると考えられている領域が、各種証明書への応用です。たとえば学生証をSBTとして発行すると、学生証の偽造や学割の悪用を防ぐことができます。悪用を排除できれば、企業や学校側がより良いサービスを提供してくれる可能性もあるでしょう。卒業後には卒業証書として活用することで、経歴詐称などを防ぐこともできます。
また、SBTは譲渡はできませんが、バーン(焼却)はできるので、一時的に個人情報と結びつけたい場合にも使用できます。たとえば借用書などをSBTとして発行した場合、借金を完済した時点でSBTをバーンすることができます。
このようにSBTは、Web3時代のデジタルIDとしての活用が期待されています。
ファントークン
ファントークンとは、ファンとブランドの関係構築を目的としたトークンです。現在、ファントークンは主にスポーツ業界で利用されており、マンチェスターシティやバルセロナFCなどの世界的に有名なスポーツチームからUFCなどのプロ格闘技団体に至るまで、数多くの団体がファントークンを活用しています。
デジタル会員証としてのトークンを所有することによって、チームや選手に対してさらに愛着が持てるようになったり、ファンコミュニティの中で「自分は正真正銘のファンだ」といった心理的な優越感を得ることができます。
また、チケットの先行抽選やユニフォームのデザイン投票への参加権など、特典付きのトークンも存在します。このようにファントークンは特別体験や特典を通じてファンとのエンゲージメントを高めていくことを可能にしてくれるのです。
さらに、ファンに対してだけではなく選手やチームにとってもメリットをもたらします。それは、コンテンツの2次流通を収益化できるという点です。
これまでのチームや選手にとっての主な収入源は、試合日のチケット代や物販、そして各種中継といったコンテンツの一次利用によるものでした。一方、あらゆるコンテンツやデータがトークンに紐付けられることで、転売による二次流通による利益がチームや選手に還元される仕組みが実現可能となります。
例えば、新人時代に書いたサインが有名になってから高値で取引されるようになると、選手自身にもその利益が還元され、活躍次第で大きな収入源となる可能性があります。同様に、優勝決定戦などのプレミア価格がついたチケットの転売利益を、チームに還元することも可能となります。
こうしたマネタイズの観点からもファントークンには多くの期待が寄せられています。
トークンを活用したビジネスをするうえで気をつけるべき点
これまで見てきたように、同じ暗号資産であるコインとは一線を画しつつも、様々な種類ごとに多くのメリットと活用先があるトークンですが、ビジネス活用をする際には気をつけなければいけないポイントがあります。
ここからはこうしたトークンビジネスの注意点について解説します。
法整備が完全に整っているわけではない
まず第一に、法整備が整っていない点が挙げられます。セキュリティトークンは金商法の改正などが大々的に行われましたが、日本は暗号資産関連の法整備が欧米諸国に比べて全体的に遅れています。
したがって、事業者側は販売資格やビジネスモデルそのものが法律に抵触しないか注意深く調査する必要があり、購入者側は、トークンの売却益などに発生する税金などについて適切な手続きをしなければなりません。
また、こうした状況も踏まえて各トークンの流通市場は慎重な姿勢をとっています。理論上は、様々なプラットフォームで売買可能なトークンであっても、マーケットの整備が追いつかずに流動性で劣っているケースも散見されます。
したがって法整備・流通市場の整備には引き続き注意しなければならないでしょう。
詐欺のイメージを払拭する必要がある
2つ目は詐欺のイメージが付きまとっている点です。トークン自体は個人であっても発行者になることができ、簡単に資金を集められる便利な資金調達法として活用できます。一方で、暗号資産が世に広まった当初、架空のプロジェクトへの投資話や「絶対に儲かる」といった詐欺プロジェクトが社会問題になり、「暗号資産(仮想通貨)=怪しい」というイメージが定着してしまいました。
現在でも個々のトークンについては一般的な知名度はあまり高くなく、まだまだ市場へ浸透しているとはいえない状況です。したがって、トークンの発行企業はホワイトペーパーを公表するなどして市場の理解を得ることが重要です。
トークンのラインナップが乏しい
3つ目はトークン商品のバリエーションが多くはないということです。NFTであればアートやゲーム、セキュリティトークンであれば不動産、ファントークンであればスポーツ業界というように、それぞれのトークンと相性の良いジャンルではすでにトークン化が行われてきました。
したがって、単純に話題作りのために類似トークンを発行したり、トークンの本質から逸れるような企画(従来のポイントで代用できる)では、成功を収めるのは至難の業でしょう。
一方で、それだけ似たようなトークンが市場に出回っているということは、斬新な仕組みを持ったトークンや、価値の安定したトークンを打ち出すことができれば大規模なマネタイズや新たなエコシステムを創出することも可能です。
トークンを活用するうえでは、法律やイメージ面と同等に、トークンそのものの設計を消費者・投資家のニーズにマッチさせる必要があるでしょう。
まとめ:トークン設計はブロックチェーンのプロにお任せしよう
本記事ではトークンについて詳しく解説しました。
今まで見てきたようにトークンにはさまざまな意味があり、一概にトークンという言葉で全てを説明できるものではありません。しかし、トークンは組み合わせ方次第で、用途や活用先が大きく広がります。将来的には仮想通貨やブロックチェーン技術を基盤にした新しい経済圏、トークンエコノミーの形成も期待できます。取引はより安く、より早く実行されるようになるでしょう。
一方で、実際にトークンを活用したサービスをローンチするとなると、法律や技術の面で多くの課題に直面することと思います。こうした際、適切なトークン設計をしないとサービス開始後に法律違反が発覚したり、システムの脆弱性が明らかになるなど大きな問題に発展しかねません。
このような事態を避けるためにも、トークン設計はクリプト界隈の事情に精通したブロックチェーンのプロの力を借りることを強くお勧めいたします。
トレードログ株式会社は、ブロックチェーン開発・導入支援のエキスパートです。ブロックチェーン開発で課題をお持ちの企業様やDX化について何から効率化していけば良いのかお悩みの企業様は、ぜひ弊社にご相談ください。貴社に最適なソリューションをご提案いたします。
-1.png)