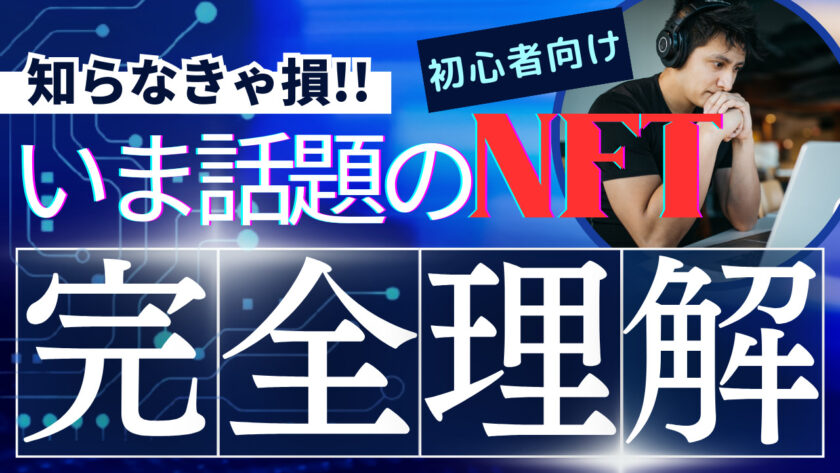当初は一部のクリプト界隈で盛り上がっていたNFTも、最近ではニュースやSNSでも取り上げられることも増えてきました。しかし、NFTの歴史はまだまだ浅く、「名前は聞いたことはあるけど、具体的にどういう技術なのか、なぜ話題になっているのかはわからない」という方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、NFTの概要からその仕組みや事例を分かりやすく解説していきます!
そもそもNFTとは?
NFT=”証明書”付きのデジタルデータ
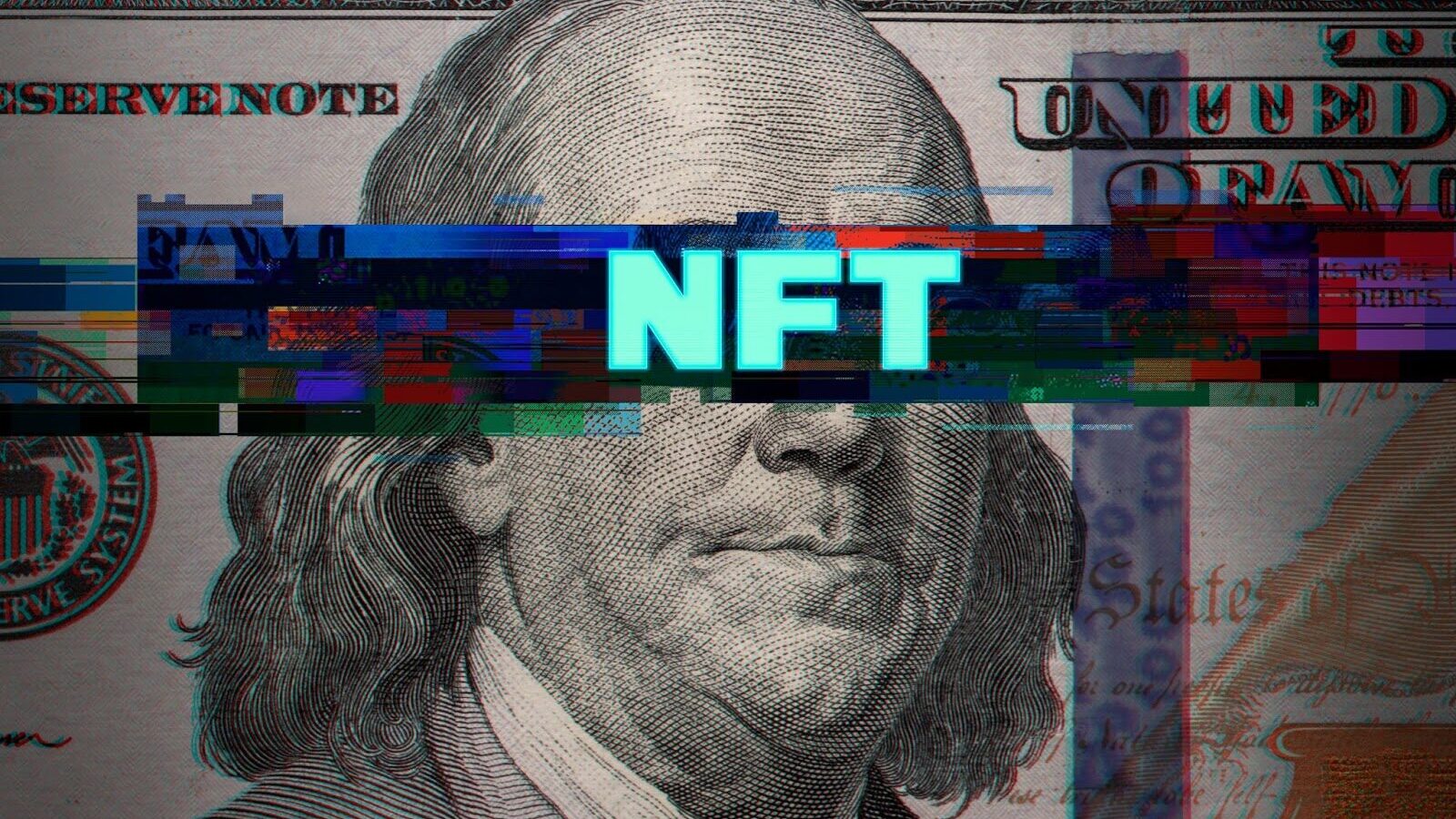
NFTを言葉の意味から紐解くと、NFT=「Non-Fungible Token」の略で、日本語にすると「非代替性トークン」となります。非代替性とは「替えが効かない」という意味で、NFTにおいてはブロックチェーン技術を採用することで、見た目だけではコピーされてしまう可能性のあるコンテンツに、固有の価値を保証しています。
つまり簡単にいうと、NFTとは耐改ざん性に優れた「ブロックチェーン」をデータ基盤にして作成された、唯一無二のデジタルデータのことを指します。イメージとしては、デジタルコンテンツにユニークな価値を保証している”証明書”が付属しているようなものです。

NFTでは、その華々しいデザインやアーティストの名前ばかりに着目されがちですが、NFTの本質は「唯一性の証明」にあるということです。
NFTが必要とされる理由
世の中のあらゆるモノは大きく2つに分けられます。それは「替えが効くもの」と「替えが効かないもの」です。前述した「NFT=非代替性トークン」は文字通り後者となります。

例えば、紙幣や硬貨には代替性があり、替えが効きます。つまり、自分が持っている1万円札は他の人が持っている1万円札と全く同じ価値をもちます。一方で、人は唯一性や希少性のあるもの、つまり「替えが効かないもの」に価値を感じます。不動産や宝石、絵画などPhysical(物理的)なものは、証明書や鑑定書によって「唯一無二であることの証明」ができますが、画像や動画などのDigital(デジタル)な情報は、ディスプレイに表示されているデータ自体はただの信号に過ぎないため、誰でもコピーできてしまいます。
そのため、デジタルコンテンツは「替えが効くもの」と認識されがちで、その価値を証明することが難しいという問題がありました。実際、インターネットの普及によって音楽や画像・動画のコピーが出回り、所有者が不特定多数になった結果、本来であれば価値あるものが正当に評価されにくくなってしまっています。NFTではそれぞれのNFTに対して識別可能な様々な情報が記録されています。そのため、そういったデジタル領域においても、本物と偽物を区別することができ、唯一性や希少性を担保できます。
これまではできなかったデジタル作品の楽しみ方やビジネスが期待できるため、NFTはいま、必要とされているのです。
NFTを特徴づける3つのポイント
データの改ざんが困難である
唯一性の証明をするためには、データが上書きされることのない高いセキュリティ性が求められます。それを実現しているのが、NFTの基盤となっているブロックチェーンです。
ブロックチェーンの定義には様々なものがありますが、噛み砕いていうと「取引データを暗号技術によってブロックという単位でまとめ、それらを1本の鎖のようにつなげることで正確な取引履歴を維持しようとする技術のこと」です。取引データを集積・保管し、必要に応じて取り出せるようなシステムのことを一般に「データベース」といいますが、ブロックチェーンはそんなデータベースの一種でありながら、特にデータ管理手法に関する新しい形式やルールをもった技術となっています。
ブロックチェーンにおけるデータの保存・管理方法は、従来のデータベースとは大きく異なります。これまでの中央集権的なデータベースでは、全てのデータが中央のサーバーに保存される構造を持っていました。したがって、サーバー障害や通信障害によるサービス停止に弱く、ハッキングにあった場合に、大量のデータ流出やデータの整合性がとれなくなる可能性があります。
これに対し、ブロックチェーンは各ノード(ネットワークに参加するデバイスやコンピュータ)がデータのコピーを持ち、分散して保存します。そのため、サーバー障害が起こりにくく、通信障害が発生したとしても正常に稼働しているノードだけでトランザクション(取引)が進むので、システム全体が停止することがありません。また、データを管理している特定の機関が存在せず、権限が一箇所に集中していないので、ハッキングする場合には分散されたすべてのノードのデータにアクセスしなければいけません。そのため、外部からのハッキングに強いシステムといえます。
さらにブロックチェーンでは分散管理の他にも、ハッシュ値やナンスといった要素によっても高いセキュリティ性能を実現しています。
ハッシュ値は、ハッシュ関数というアルゴリズムによって元のデータから求められる、一方向にしか変換できない不規則な文字列です。あるデータを何度ハッシュ化しても同じハッシュ値しか得られず、少しでもデータが変われば、それまでにあった値とは異なるハッシュ値が生成されるようになっています。
新しいブロックを生成する際には必ず前のブロックのハッシュ値が記録されるため、誰かが改ざんを試みてハッシュ値が変わると、それ以降のブロックのハッシュ値も再計算して辻褄を合わせる必要があります。その再計算の最中も新しいブロックはどんどん追加されていくため、データを書き換えたり削除するのには、強力なマシンパワーやそれを支える電力が必要となり、現実的にはとても難しい仕組みとなっています。
また、ナンスは「number used once」の略で、特定のハッシュ値を生成するために使われる使い捨ての数値です。ブロックチェーンでは使い捨ての32ビットのナンス値に応じて、後続するブロックで使用するハッシュ値が変化します。コンピュータを使ってハッシュ関数にランダムなナンスを代入する計算を繰り返し、ある特定の条件を満たす正しいナンスを見つけ出す行為を「マイニング」といい、最初にマイニングを成功させた人に新しいブロックを追加する権利が与えられます。
ブロックチェーンではマイニングなどを通じてノード間で取引情報をチェックして承認するメカニズム(コンセンサスアルゴリズム)を持つことで、データベースのような管理者を介在せずに、データが共有できる仕組みを構築しています。参加者の立場がフラット(=非中央集権型)であるため、ブロックチェーンは別名「分散型台帳」とも呼ばれています。
このようなブロックチェーンが持つ高いセキュリティ技術によって、NFTは安全に管理されています。ブロックチェーンについて詳しく知りたいという方は、こちらも併せてご覧ください。
プログラマビリティがある
NFTには「プログラマビリティ」と呼ばれる特徴があり、あらかじめ設定されたプログラムによってさまざまな機能を持たせることができます。これにより、単なるデジタル資産にとどまらず、クリエイターやユーザーにとって新しい価値を生み出す仕組みを作ることが可能になっています。
NFTが二次流通した際にクリエイターや発行者に手数料が還元されるように設計したとしましょう。従来の中古市場では、作品が売買されてもクリエイターには利益が入らないのが一般的でしたが、NFTでは売買が繰り返されるたびに一定の収益が発生します。これにより、アーティストやコンテンツ制作者は継続的に収益を得ることができ、著作権管理の煩雑さも軽減されるメリットが生まれます。
また、エアドロップという仕組みを使えば、特定のNFTを一定期間保有している人に新しいNFTを自動的に配布することができます。例えば、あるスポーツチームがファン向けにNFTを発行し、そのNFTを一定期間持ち続けた人だけに特別なデジタルアイテムをプレゼントするといった設計にすれば、NFTの長期保有を促したり、ファンコミュニティを活性化させることにもつながるでしょう。
このように、NFTはただのデジタルアイテムではなく、プログラムによって機能を自由に追加できる点に大きな特徴があります。その使い方次第で、ビジネスモデルやファンエンゲージメントのあり方も変わっていくでしょう。
誰でも売買できる
NFTはオンライン上で売買できるため、マーケットプレイスと呼ばれる取引所にアクセスすれば、誰でも簡単にアートやデジタルコンテンツの売買に参加できるようになりました。これまで、アート作品を販売するにはギャラリーやオークションハウスを通す必要がありましたが、NFTの登場によって、個人でも手軽に作品を出品し、世界中のユーザーと直接取引できる環境が整っています。
多くのマーケットプレイスでは、入札制度が導入されており、購入希望者が競り合うことで、作品の価値が市場の需要に応じて適正な価格で決定される仕組みになっています。これにより、特定のバイヤーやギャラリーに依存せず、誰でも公平に作品を取引できるようになりました。さらに、専門的な知識がなくても、デジタルコンテンツをNFT化できるサービスが充実しており、アーティストやクリエイターが気軽に作品を発表できる環境が整っています。
NFTの敷居の低さを象徴する例として、小学生が制作したNFTが話題になったケースがあります。小学3年生の男の子が夏休みの自由研究として作成したドット絵作品「Zombie Zoo」は、たった3ヶ月で200点が販売され、取引総額が4400万円を超えるなど、大きな注目を集めました。こうした成功事例が生まれるのも、NFTが年齢やキャリアに関係なく、誰もが市場に参加できるオープンな仕組みであることを示しています。
小3男児の絵に「一時2600万円」…高値売買の動きを急拡大させた「NFT」
NFTは、従来のアート市場やコンテンツ流通のあり方を大きく変え、クリエイターとファンが直接つながる新しい時代を切り開いています。特別なスキルや大きな資本がなくても、自分の作品を世界中の人々に届けることができるというのは、NFTならではの魅力といえるでしょう。
NFTはなぜ話題に?
NFTが話題になった大きな理由の一つは、信じられないような高額の取引でしょう。
2021年3月22日には、『Twitter』の共同創設者兼最高経営責任者(CEO)のジャック・ドーシー(Jack Dorsey)によって2006年に呟かれた ”初ツイート” がNFTとしてオークションに出品され、約3億1500万円という驚愕の金額で売却され大きな話題を集めました。
TwitterのドーシーCEOの初ツイートNFT、3億円超で落札 全額寄付 – ITmedia NEWS
また、同年3月にデジタルアーティストであるBeeple氏がNFTアートとして競売に出したコラージュ作品「Everydays: the First 5000 Days」が6900万ドル(日本円で約75億円)という値が付きました。これは、オンラインで取引されたアーティストのオークション価格史上最高額を記録し話題を呼びました。
老舗Christie’s初のNFTオークション、デジタルアートが約75億円で落札 – ITmedia NEWS
「デジタルデータにこんな価値が!」というインパクトや話題性から、NFTという言葉が一気に広まっていったのはある意味当然ですね。ただし、私たちが注意すべき点は、全てのNFTの価値は安定しているわけではないということです。
ある人が大事にとってある ”思い出の石ころ” に値段がつかないのと同様、そのデジタルデータに対して価値があると多くの人々が判断し、需要や投機性が生まれてようやくそのNFTに値段がつくのです。
デジタルデータに価値が付き売れるようになり、NFTが時代の大きな転換点となったことは事実ですが、過剰な需要と供給が加熱してしまうと仮想通貨と同様、バブル崩壊の道を辿るかもしれません。
NFTはどこで取引されている?
NFTを売買するには、NFTマーケットプレイスを利用します。アートや音楽、映像、ゲームのキャラクターやアイテムなどの売買ができるさまざまなNFTマーケットプレイスがあります。
NFTマーケットプレイスは先述のブロックチェーン技術を土台としており、マーケットプレイスごとに土台とするブロックチェーンの種類も異なります。
現在世界最大手のOpenSeaをはじめ、LINE NFTやCoincheck NFTといった様々なNFTマーケットプレイスが国内外に存在し、取り扱いコンテンツや決済可能な暗号資産もそれぞれ異なるため、出品者や購入者は取引する場所を用途に合わせて選ぶ事ができます。
詳しくは以下の記事で解説しています。
NFT活用のユースケースとは?
NFT×アート
絵画やアートの分野でも、NFTの技術が使われ始めています。
多くの場合、アートや絵画はPhysical(物理的)なものとして作られる場合がほとんどです。NFT登場前のデジタルアート作品はコピー・複製が可能なため、高い価値をつけるのが難しいというのが現実でした。しかし、NFTの技術により、コピー不可能なデジタルアートを作成できるようになり、先述したBeeple氏のように75億円で取引されたNFTアートも存在しています。
ちなみに日本国内では、村上隆氏やPerfumeといった著名人が、続々とNFTアートを発表しています。国内のアート分野でもNFT技術の活用が徐々に広まっていると言えるでしょう。
NFT×ゲーム
NFTの活用が盛んに行われてきた事例がゲーム分野での利用です。
NFT技術を利用することで、自分が取得した一点物のキャラクターやアイテムをプレイヤー同士で売買することや、あるタイトルで取得したキャラクターやアイテムを他のゲームで使うことも可能になります。ゲーム内で育成したキャラクターなどは二次流通市場で取引され、パラメータやレアリティが高いほど高値で取引されています。
また、NFTは往々にして仮想通貨を用いて取引がされることが多いです。そのため、ゲームをプレイすることで仮想通貨を得られる「Play to Earn(遊んで稼ぐ)」という概念が生まれており、これは今までのゲーム体験を覆すものでしょう。今後も、NFTの特色を生かしたブロックチェーンゲームが次々にリリースされることが期待されています。
NFT×スポーツ
スポーツ業界においてNFTは、選手やクラブと、ファンのエンゲージメントを高める手段として活用されています。
『世界的に有名なプロスポーツ選手の決定的な名シーン』には、代えがたい価値があるはずです。誰もが感動しますし、ましてやファンにとっては垂涎の価値です。しかし、インターネット上には『決定的な名シーン』がたくさん転がっていて、お金を払うことなく誰もが気軽に見ることができてしまいます。
そこでNFTによって選手や選手のプレーをNFT化すれば、その瞬間を切り取った「公式」のデジタルコンテンツが唯一無二のアイテムとして色褪せずに存在することができ、ファンが所有する喜びを感じたり、ファンの間で売買できるようになります。
また、売り上げの一部をクラブに還元することで、応援しているチームに貢献しながら楽しむことができるというまさにファンには二重に嬉しい構造になっていることも、スポーツ界でNFTが広まりつつある理由でしょう。
NFT×トレカ
現在、最も勢いのあるNFTの活用分野はなんといってもNFTトレカ、すなわちトレーディングカードです。
トレカ界隈では現在、印刷技術やスキャンソフトの発達によって偽造品の氾濫が大きな問題となっています。偽物のクオリティが上がるだけではなく、実店舗でも偽物の販売で検挙されているケースがあり、もはや一般人の私たちからすると見分けることは困難です。
NFTでは前述の通り、偽造やデータの改ざんができません。したがって、一点モノであるレアカードの証明や偽造防止という観点では、まさにうってつけの技術なのです。
実物のトレーディングカードは、一部の熱心なコレクターに支持されるマニアックな世界という印象があったかもしれません。しかしNFTトレカでは、人気アイドルやプロスポーツ、人気アニメのトレカが発売されるなど、幅広い層に提供されています。
アツい盛り上がりを見せているだけに今後も要注目の組み合わせです。
NFTの将来性
NFTはオワコン?
このように様々なジャンルで盛り上がりを見せているNFTですが、その取引はピーク時と比べると落ち着いてきています。一部ではそういった現状を受け、「オワコン」とも囁かれていますが、果たしてNFTは将来性がないのでしょうか。
これはガートナー社が発表しているハイプサイクルです。ハイプサイクルとは、特定の技術の成熟度や社会への適用度を視覚的に表したグラフのことで、IT分野における重要な指標の一つとして知られています。
このサイクルではNFTは現在「過度なピーク」を過ぎ、「幻滅期」に突入しています。ガートナー社の定義では、幻滅期は実験や実装で成果が出ないため、関心が薄れ、この時期を通り抜けると具体的な事例をもとに社会全体で主流採用が始まるとされています。
つまり、ある意味では想定内の落ち込みで、このNFT氷河期とも言える冬の時代を耐え忍んでこそ社会への浸透が進むというわけです。したがって、この一時的な落ち込みを見て「NFTは終わった」「NFTは将来性がない」と判断するのはまだ早すぎるでしょう。
実際に、ハイプサイクルにおいてようやく幻滅期を抜け出した「人工知能」も、過去にはディープラーニングを加速させる学習データが不足していることなどを理由にブームが終焉し、「AIによって人間の仕事が奪われる!」といった主張も鳴りを潜めてきました。
しかし、現在の状況はどうでしょうか。様々な企業のサービスにAIが組み込まれ、子供からお年寄りまで誰しもが一度はAIによるユーザー体験をしているはずです。とくにアメリカのAI研究所であるオープンAIが開発した会話型AIのChatGPTは、官公庁や教育の場面で採用されるほど社会に広く浸透しました。
このように、NFTの「取引量」「時価総額」に関するネガティブなニュースは一時的な情報に過ぎません(その逆も然りで、ポジティブなニュースにも注意が必要)。むしろ、様々な要因によってNFTは着実に次への一歩を踏み出し始めています。
NFTはネクストフェーズへ
NFTが再び社会で受容される頃には、以前のような視覚的な価値の裏付けといった立ち位置ではなくなっているかもしれません。
確かにNFTは現在、投機的な側面から人気を博しています。しかし、むしろ今後はNFTないしブロックチェーンの「データの改ざんが困難」という特徴を生かし、所有権証明や身分証明といった非金融分野への普及が進んでいくでしょう。
その事例の一つが「SBT(SoulBound Token、ソウルバウンド・トークン)」です。SBTは譲渡不可能なNFTであり、二次流通での売買や譲渡などが一切できません。この性質を利用して、現在デジタルID(本人確認、学歴・社歴証明、身体・医療情報など)での活用が検討されています。
また、多くのNFTがイーサリアム(Ethereum)上に構築されていますが、これ自体の技術的進化もNFTが再興するための一要因です。NFTのデメリットの一つに「手数料の高騰」があります。手数料は、ブロックチェーンへの記録や取引所の仲介により避けられないモノですが、イーサリアムはその手数料が他のチェーンに比べると割高でした。しかし、イーサリアム(Ethereum)自体のアップデートにより、処理速度が向上すれば、手数料のユーザー負担は改善されることでしょう。
また、ポリゴン(Polygon)など第3のブロックチェーンの活躍も見逃せません。ポリゴンの処理スピードはイーサリアムの約450倍ともいわれており、取引手数料もはるかに安く済みます。スターバックスやナイキといった数々のブランドの取り組みにも採用されていることからも、その期待が窺い知れます。
このようにNFTは、これからのデジタル社会を大きく変化させる原動力として、その姿かたちを変えつつあるのです。
まとめ
これまで人類は、土地や物といった物理的な物を所有し価値を高め、売買・交換することで経済活動を行ってきました。それと同じことがデジタル領域でも起こりうるということです。
かつてインターネットやスマホ、SNSが目新しいモノでしたが、今では誰もが当たり前のように使いこなし、社会・人々の生活を一変させました。NFTも同様に今後の社会を変える大きな可能性を秘めています。
今後も引き続きキャッチアップが欠かせないでしょう。
-1.png)