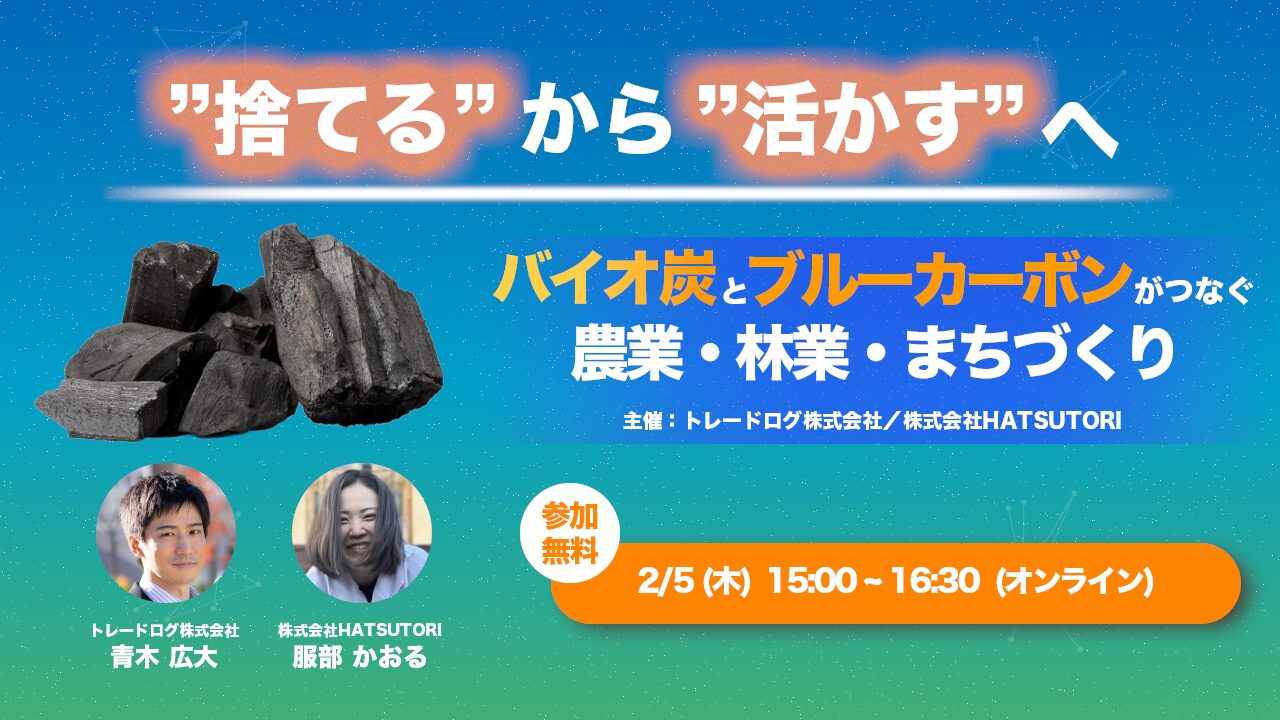近年、食品やファッション業界で高まる製品の安全性や倫理意識。この潮流は美容・コスメ業界にも及び、サプライチェーンの透明性確保が急務です。そこで注目されるのがブロックチェーン技術。改ざん困難な分散型台帳は製品の真正性を証明し、原材料から販売までの過程を可視化することで、消費者はスマホで原産地や製造過程を確認でき、安心へと繋がります。
さらに、ブロックチェーンは顧客との新しい関係も構築します。トークン(NFT)発行はロイヤリティを高め、コミュニティ形成を促進し、限定アクセスや特典、ブランド体験といった特別な体験によって顧客エンゲージメントを深化させる可能性があるのです。
本記事では、美容・コスメ業界のブロックチェーン活用事例をご紹介。トレーサビリティ実現、顧客エンゲージメント向上、業界透明化への貢献を解説します。ブロックチェーンが美容・コスメ業界の未来をどう変えるのか、その可能性を探ります。
そもそもブロックチェーンとは?
ブロックチェーンは、サトシ・ナカモトと名乗る人物が2008年に発表した暗号資産「ビットコイン」の中核技術として誕生しました。ブロックチェーンの定義には様々なものがありますが、噛み砕いていうと、「取引データを暗号技術によってブロックという単位にまとめ、それらを鎖のようにつなげることで正確な取引履歴を維持する技術」です。一般的なデータベースとは異なり、中央管理者が存在せず、ネットワークに参加する複数のコンピュータ(ノード)が対等な立場でデータを管理する「P2P型(ピア・ツー・ピア)」の仕組みを採用しています。
従来のクライアントサーバ型のデータベースでは、単一の中央サーバーがデータを管理しますが、これには「単一障害点(SPOF:Single Point of Failure)」というリスクがあり、サーバーが攻撃や故障により停止すると、システム全体が機能しなくなる可能性があります。一方、ブロックチェーンでは、すべてのノードが同じデータを保持するため、一部のノードがダウンしてもネットワーク全体の運用に影響を与えません。
また、ブロックチェーンのデータはその名前の通り、一定量の取引情報を1つの「ブロック」にまとめ、それを時系列順に「チェーン」のようにつなげていくことで管理されます(各ブロックチェーンによってブロック生成・承認の仕組みは異なるのですが、ここでは代表的なブロックチェーンであるビットコインを例に説明します)。このブロックをつなぐ際に使われるのが「ハッシュ値」と呼ばれる識別子です。
ハッシュ値とは、あるデータを関数(ハッシュ関数)に入力すると得られる一意の数値のことで、「あるデータを何度ハッシュ化しても同じハッシュ値しか得られず、少しでもデータが変われば、それまでにあった値とは異なるハッシュ値が生成される」という特徴を持ちます。いわば、指紋のようなものですね。これにより、過去のデータが変更された場合、そのブロック以降のハッシュ値がすべて変わってしまうため、不正を検知しやすくなっています。
さらに、新たなブロックを生成するには、ある特定の条件を満たすハッシュ値を導く必要があります。ブロックの生成者は変数(=ナンス)を変化させながら、ブロックのハッシュ値を計算していき、最初に条件を満たすハッシュ値を見つけた作業者(=マイナー)が、そのブロックの追加権を得て、報酬として新しい暗号資産を獲得する仕組みです。
しかし、この一連のプロセス(=マイニング)には膨大な計算リソースが必要であり、データを書き換えたり削除するのには、強力なマシンパワーやそれを支える電力が必要となるため、現実的には改ざんがとても難しいシステムとなっています。
詳しくは以下の記事で紹介しています。
このような特性を持つブロックチェーンは、金融分野だけでなく、サプライチェーン管理やカーボンクレジット取引など、データの透明性と信頼性が求められる分野で幅広く活用されています。次のセクションでは、美容・コスメ業界においてブロックチェーンがどのように利用されているのか、具体的な事例を紹介していきます。
美容・コスメ業界のブロックチェーン導入事例5選
ブロックチェーンの基本を押さえたところで、ここからは美容・コスメ業界における具体的な導入事例を見ていきましょう。トレーサビリティの担保や新たな顧客体験など、さまざまな用途で活用が進んでいます。それぞれの事例について、どのような課題を解決し、どんなメリットをもたらしているのかを詳しく解説します。
クラランス(CLARINS):トレーサビリティ確保による安心安全なブランドの確立
フランス発のプレステージスキンケアブランド「クラランス(CLARINS)」は、消費者により安心して製品を使用してもらうため、2023年8月29日よりブロックチェーン技術を活用したトレーサビリティシステム「クラランス トラスト(T.R.U.S.T.)」の日本展開を開始しています。
トレーサビリティとは、「Trace(追跡)」と「Ability(能力)」を組み合わせた造語で、一つの製品が「いつ」「どこで」「誰に」よって作られ、流通し、販売されているのかを把握する仕組みのことです。日本では牛肉の産地偽装や消費期限切れの食品の販売などが大きな問題となったことがきっかけで、「トレーサビリティ」という言葉を耳にする機会が増えましたが、美容・コスメ業界でのトレーサビリティの意味も同じく、アイテム一つ一つの製造工程や製品を倉庫や店舗に配送する物流工程、消費者が手に取るまでの全ての工程を指します。
このサービスの最大の特徴は、公式サイトや製品に記載されたQRコードを通じて、配合されている植物の種類や原産地、製造工程を簡単に閲覧できる点です。特に、各製品に固有のバッチコードを入力することで、製造年月日まで特定できる仕組みは、製造業などではよく見る仕組みですが、化粧品業界において画期的な試みといえるでしょう。老若男女問わずにスキンケアへの関心が高まっている現代では、消費者が自分が使用している製品がどのように作られたのかを明確に知ることができるというのは、嬉しいポイントですよね。
現在、クラランス トラストの対象商品は“トータル クレンジング オイル SP”など39アイテムに及びますが、2025年までにはすべてのスキンケア製品をこのシステムで管理することを目標としています。このプロジェクトの名称「T.R.U.S.T.」には、T(traceability、追跡可能)、R(responsibility、責任ある)、U(uniqueness、独自の方法)、S(security、安全性の担保)、T(transparency、透明性)といったブランドの理念が込められており、単なるデジタル技術の導入にとどまらず、クラランスが長年培ってきた信頼性と品質へのこだわりを反映しています。
1954年の創業以来、同社は植物の可能性を信じ、ユーザーの声に耳を傾けながらスキンケア製品を開発してきました。今回のトレーサビリティシステムの導入も、その姿勢の延長線上にある取り組みであり、より安全で高品質な製品を届けたいという想いが込められています。消費者の関心が高まる中、こうした透明性を確保する努力は、ブランドの信頼性をさらに強化する要素となるでしょう。今後の展開にも期待が寄せられます。
資生堂:テーラーメイドな顧客サービスを実現するブランド体験
その人にしかない美しさを引き出す——。そんな理想を叶えるため、資生堂グループのプレステージブランド「THE GINZA」は、ブロックチェーン技術を活用した新たなブランド体験の提供に乗り出しています。
2021年に行われた、スキンケア製品10アイテムのリニューアルでは、よりパーソナライズされた体験を提供するため、RFIDを商品に貼付。購入者が製品パッケージから専用のURLにアクセスしてユーザー登録を行うことで、個々の顧客に最適化されたサービスを受けられる「テーラーメイドな顧客サービス」の仕組みを構築しています。
ここで活用されているのが、トレードログ株式会社が開発したIoT連携ブロックチェーンツール「YUBIKIRI(ユビキリ)」です。デジタル技術を通じて、リアルとオンラインの体験をシームレスに結び付けることを可能にしており、公式ECと店舗との連動によってブランドが持つ世界観や高級感を損なうことなく、ユーザー一人ひとりに最適な接客がデジタル上でも行えるようになります。
このシステムの導入背景には、グローバル市場における3つの課題がありました。1つは、オンラインとオフラインを連携させたO2Oマーケティングの必要性。2つ目は、海外市場を中心に拡大する偽造品対策。そして3つ目は、複雑化するサプライチェーン管理(SCM)の合理化です。従来はそれぞれ個別に対応していたこれらの課題を、「YUBIKIRI」の導入によって一貫して解決しようというのが今回の狙いです。
この技術のベースとなっているのは、マイクロソフトのクラウドプラットフォーム「Microsoft Azure」と、米国Kaleidoが提供する「Kaleido BaaS」。さらに、高い秘匿性と柔軟な拡張性を兼ね備えるブロックチェーン基盤「Quorum」を使用することで、ユーザー体験を損なうことなく、安全かつ信頼性の高い仕組みを実現しています。
かつては、ブロックチェーン技術といえば金融やセキュリティ分野の専売特許のように見られていましたが、今やラグジュアリーコスメの世界にも浸透しはじめています。特に本プロジェクトのような、マーケティングとサプライチェーン管理という“両輪”をまたぐ本格導入は、ラグジュアリー化粧品市場において世界初となる事例です。
技術の導入がゴールではなく、顧客との信頼関係を深める手段として位置づけられている点にこそ、このプロジェクトの真価があります。資生堂グループの長年にわたるブランド哲学と、最先端のテクノロジーが融合したこの取り組みは、化粧品の世界における「体験価値」のあり方を塗り替える可能性を秘めており、今後の展開にも注目です。
GIVENCHY:NFTで彩るメゾンの誇りと“美と多様性”の新しいカタチ
世界的ブランドであるGIVENCHY(ジバンシイ)は、化粧品業界の中でもいち早くNFTアートに取り組んだ先駆者として知られています。NFTは「非代替性トークン(Non-Fungible Token)」の略で、一言でいえば「本物であることを証明できるデジタルデータ」を意味します。通常の画像や動画は簡単にコピーができますが、NFTには所有者や履歴といった情報がブロックチェーン上に記録されており、「誰が持っているか」「本物かどうか」をはっきりと証明することができ、アート作品としての価値がデジタル上でも保証されるのです。
そんなNFTの特性を活かして、GIVENCHYは単なるデジタルアートの販売ではなく、社会的なメッセージを込めたプロジェクトを展開しています。2022年に発表された初のコレクション「Pride II」では、LGBTQIA+の支援を目的に、ロンドンのギャラリーオーナーで活動家でもあるアマール・シン氏と、アーティスト集団「リワインド・コレクティブ」とのコラボレーションによって1,952点のデジタルアート作品を制作しました。
このNFTアートは、ジバンシイを象徴するアイテム「プリズム・リーブル」とレインボーフラッグのカラーを融合させたビジュアルが採用されており、「多様性」「自己表現」「平等」といったテーマが込められています。注目すべきは、販売によって得られた収益約128,000ドル(当時の日本円で約1,400万円)を、フランスのLGBTQIA+支援団体「Le MAG Jeunes LGBT+」に全額寄付した点で、ブランドとして「どのような価値観を大切にしているのか」を世界中に伝える機会となりました。
また、GIVENCHYはNFTにとどまらず、仮想現実と社会性を融合したインターネット上の新たな空間であるメタバースの領域にも積極的に展開しています。人気のオンラインゲーム「Roblox(ロブロックス)」とのコラボーションでは、「Givenchy Beauty House(ジバンシイ・ビューティーハウス)」というイベントを設け、ゲーム内でメイクアップやファッション体験ができる仕掛けを提供しました。
こうした同ブランドのブロックチェーン活用は、企業のデジタル活用が「売るため」だけでなく「語るため」にも用いられる時代であることを象徴しています。特に美容業界では「美しさ」の定義がより多様化している中で、GIVENCHYが示した姿勢は他のブランドにも大きな示唆を与えました。従来の広告とは異なり、遊びを通じてブランドの世界観に自然に触れてもらうという、非常に現代的なマーケティング手法は、「美」と「社会性」を両立させた新しいブランディングの形として今後も語り継がれていくことでしょう。
KIKI World:ファッションアイテムとWeb3.0の融合による共創型コスメ
コスメブランドと聞くと、多くの人が頭に思い浮かべるのは広告やパッケージの美しさ、あるいは発色やテクスチャーの違いかもしれません。しかし、KIKI Worldはその常識を大きく覆してくれる、Web3時代に適応した“共創型”のコスメブランドとして登場しました。
このブランドの面白さは、化粧品そのものの機能や品質だけでなく、「誰が、どのように作ったのか」「どんな思いでこの色が生まれたのか」という商品のバックグラウンドにまでこだわっている点にあります。そして、そこにはブロックチェーン技術やNFC(近距離無線通信)といった最新テクノロジーが活躍しています。
一般的なブランドが自社で商品企画から発売までを完結させるのに対し、KIKIではコミュニティのメンバーが積極的に意思決定に関与します。「このカラーはどう?」「次に発売するのはどんなテクスチャーがいい?」という問いかけに、ユーザーは毎日投票で答えることができ、それが製品に反映されていきます。さらに、この投票行動はポイントとして可視化され、商品購入時の割引や限定コンテンツとの交換にも利用可能です。このようなインセンティブ設計が可能なのも、柔軟性・透明性に優れるブロックチェーンの良さですね。
中でも話題を呼んだのが、2023年に登場した「NFCチップ付きネイル」でした。ネイル本体に直接チップが内蔵されており、スマートフォンを近づけると、ユーザーのプロフィールとリンクされ、SNSのように他者とつながることができます。まるで“自己紹介ができるネイル”とも呼べるこのプロダクトには、SNS世代の若者たちを中心に大きな関心が寄せられました。
実際に、トルコのイベントでこのネイルが披露された際には、SNSのX上で100万回以上のインプレッションを記録。アジア、ヨーロッパ、アメリカといった各国のメディアにも取り上げられ、単なるガジェットではない、新しいコミュニケーションの形として受け入れられていきました。自分の手先が名刺代わりになる──そんな未来を、KIKI Worldは当たり前にしようとしています。
このような同社の姿勢に世界最大級の化粧品企業であるエスティ ローダー カンパニーズ傘下の投資ファンド「NIV(ニュー インキュベーション ベンチャーズ)」も共感を示しており、2022年11月には米国のベンチャーキャピタルA16Zと共にKIKIへの出資を決定。700万ドル、日本円にして約10億円を超える大型投資として注目を集めました。
KIKI Worldの取り組みには、「コスメ=完成品を買うもの」という従来の感覚を覆すヒントが詰まっています。作る人と使う人の境界線をあいまいにし、関わった人すべてに何かしらの“見返り”がある。そんな斬新なものづくりの形が、NFCネイルという小さなチップから、すでに始まっているのかもしれません。
BIZKI:NFTを活用したコスメユーザーのスポンサー体験
化粧品を応援する方法が「買う」だけではなくなったことに、本当に驚かされます。コスメブランドBIZKIの新ブランド「/me.(シェイクミー)」が取り組んだ「スポンサーNFT」は、まさにその象徴といえるものでした。NFTというと、これまでアートやデジタルコンテンツの所有権を証明するものとして使われることが多かったですが、本アイテムでは商品そのものの支援者として「スポンサーになる」という立ち位置を、個人が簡単にNFTを通じて獲得できるようになっています。
実現のポイントは「QRコード連動型スポンサーNFT」にあります。同ブランドのパッケージには専用のQRコードが印刷され、そこから誰でも簡単にNFTを購入できるようになっており、購入者は自分のTwitterアカウントと名前をリンクさせることで「私はこの商品を応援しています」とアピールできる仕組みです。まるでアイドルのファンやスポーツクラブのサポーターになったかのような感覚を楽しめるのです。
商品に込めた想いやビジュアル面にも細やかな工夫があり、NFTには「/me.」の世界観を象徴するオリジナルイラストが用いられており、美容液とオイル層が混ざり合っていく様子を、女性の内なる輝きと重ねて描いています。スポンサーNFTは転売も可能で、そのたびに最大10%が企業に還元されるという持続的な収益構造を持っています。さらに、売上はすべて乳がん啓発のためのNPOに寄付されるという社会貢献の側面も含まれており、「応援が価値になる」という理念を現実のものとしています。
こうした同社の取り組みは、化粧品ブランドに限らず、今後あらゆる商品が、NFTを通じて「応援される存在」へと変わっていく可能性を秘めています。これまでの「企業→消費者」という一方通行ではなく、消費者自身が「私はこのブランドに関わっている」と感じられるようになることで、ブランドへの愛着もより深く、持続的なものになるはずです。企業の資金調達手段として、あるいはファンづくりの新たな選択肢として、スポンサーNFTという考え方がどこまで広がるのか、今後の展開に引き続き注目です。
導入における課題と懸念点

ブロックチェーンは魅力的な技術ですが、導入となると「難しそう」「コストがかかるのでは?」という声が少なくありません。実際、いくつかの壁が存在するのも事実です。
まず、よく挙がるのが技術者不足。ブロックチェーンは比較的新しい分野であるため、システム開発を任せられるエンジニアがまだまだ限られているのが現状です。特に、コスメ業界では実物のテクスチャーや色味、香りといったリアルな体験を軸にした差別化が主流で、デジタル領域での顧客体験設計にはまだ手探りの企業も多いのが実情です。その状態で、ブロックチェーンのような新しい技術にゼロから取り組むには、相応の労力と専門知識が求められます。
次に見逃せないのが、運用コストの問題です。ブロックチェーンの中でも、特にパブリックチェーンを利用する場合、トランザクションを処理するたびに「ガス代」と呼ばれる手数料が発生します。これは、NFT発行やトークン配布といった操作ごとに都度発生するもので、企画の規模によっては無視できないコストになることも。また、システムを安定的に稼働させるためのノード運用やクラウド利用料といったインフラ面の支出も継続的に発生します。投資対効果が見えづらい初期段階では、「本当にそこまで投資する価値があるのか?」と社内での説得に難航するケースも想定されるでしょう。
そして、もう一つ忘れてはならないのがユーザー側の理解度です。NFTやウォレット、トークンといった用語は、まだまだ一般消費者にとって馴染みの薄いものです。例えば、限定コスメの購入時にNFT証明書が付くとしても、「それって何に使えるの?」「どうやって見ればいいの?」と疑問を抱かれる可能性は高いでしょう。せっかくの施策も、ユーザー体験としてうまく伝わらなければ、逆に混乱や離脱につながってしまうかもしれません。
こうした複数の懸念点をひとつずつクリアしていくには、やはり信頼できるパートナーの存在が欠かせません。単なる開発だけでなく、「何から始めるべきか」「どんな形が自社に合っているのか」といった戦略面から一緒に考えてくれるブロックチェーンの専門家に相談することで、導入のハードルはぐっと下がります。
中小ブランドでも導入可能?スモールスタートの可能性
「ブロックチェーンって、大手企業が使うものじゃないの?」
そう思われる方も少なくありません。確かに、過去の事例では、ラグジュアリーブランドや世界的企業がNFTやトレーサビリティを活用するケースが多く、「予算も体制も整った企業だけの話」と感じるのも無理はないでしょう。しかし実際には、中小規模のブランドだからこそ、ブロックチェーンを差別化要素としてうまく活用できる可能性があるのです。

例えば、コスメ業界では「こだわりの原料」「生産者とのつながり」「動物実験フリー」など、ブランドの世界観や信念を大切にしている企業が少なくありません。こうしたストーリーをただ商品ページに書くだけではなく、改ざん不可能な形で“証明”として残すことができれば、ブランドへの信頼感は大きく高まります。
また、最近では「NFT付き限定コスメ」や「購入者に特典としてデジタルアイテムを配布する」など、マーケティング施策としてのブロックチェーン導入も増えています。これらは、実店舗を持たないブランドやEC中心の小規模ブランドでも始めやすいアプローチです。一定数以上購入したユーザーに対してデジタル会員証を配布し、次回購入時に特典を提供するといった企画も、ブロックチェーンを活用することで、手間をかけず透明性の高い形で運用できます。
もちろん、いきなりフルスケールでの導入は難しいかもしれません。しかし、最初は小さく始めて、効果を見ながら段階的に拡張していくという方法もあります。例えば、1商品だけを対象にNFT証明書をつけてみる、クラフト系の限定品にストーリー証明を導入する。そんなスモールスタートが、ブランド価値を高めるきっかけになるのです。
さらに、現在はノーコードやローコードで構築できるツールも増えており、以前よりも格段に導入のハードルは下がっています。それでも不安がある場合は、ブロックチェーンに精通した専門家に相談するのがベストです。目的やブランドの方向性に合わせて、最適なユースケースや技術的な選択肢を提案してくれるはずです。
まとめ:いま、ブランドは“信頼”をブロックチェーンで可視化する時代へ
ブランド価値を「証明できる形」で示す時代が到来しつつあります。ファンとのつながりを強化し、信頼性を担保しながら、新しいブランド体験を提供する。その手段として、ブロックチェーンは非常に強力なツールとなります。
しかし、その導入には技術的な課題や設計上の工夫が欠かせません。自社の規模や戦略に合わせた最適な活用法を見つけるには、ブロックチェーンのプロとの対話が不可欠です。
トレードログ株式会社では、非金融分野のブロックチェーンに特化したサービスを展開しております。ブロックチェーンシステムの開発・運用だけでなく、上流工程である要件定義や設計フェーズから貴社のニーズに合わせた導入支援をおこなっております。
ブロックチェーン開発で課題をお持ちの企業様やDX化について何から効率化していけば良いのかお悩みの企業様は、ぜひ弊社にご相談ください。貴社に最適なソリューションをご提案いたします。
-1.png)