冷凍技術の革新は私たちの食生活を大きく変容させました。1930年に戸畑冷蔵(現日本水産の前身)が「冷凍いちご」を販売してから100年近くが経った現在では、スーパーやコンビニで鮮度の高い食品を購入したり、あるいはファミリーレストランなどの外食産業では多種多様なメニューが低価格かつハイクオリティで提供されています。
こうした便利なサービスが確立しているのは、「コールドチェーン」という仕組みが関係しています。そしてさらに2025年現在、コールドチェーンへブロックチェーンを導入しようという動きが見られます。
本記事では、コールドチェーンやブロックチェーンのそもそもの仕組みや実際の事例に触れつつ、次世代の温度管理のあり方についてご紹介していきます。
コールドチェーンとは?
コールドチェーンとは、「生鮮食品や冷凍食品といった低温管理が必要な商品を、生産から輸送、保管といった流通プロセスを一貫して所定の温度を保つ仕組み」のことです。日本語では「低温物流体系」や「低温ロジスティクス」「生鮮SCM(サプライチェーン・マネジメント)」とも呼ばれています。
現在では冷凍食品や生鮮食品だけでなく、花卉や医薬品、電子部品などさまざまな分野でコールドチェーンが活用されており、私たちの日常生活に欠かせない技術となっています。
コールドチェーンのプロセス
コールドチェーンとは、温度管理が必要な製品を、生産から消費まで一貫して低温状態に保ちながら流通させる物流システムです。その流れは、「生産」「加工」「物流」「販売」「消費」の5つの段階に分かれ、それぞれの工程で適切な温度管理が求められます。
生産
コールドチェーンの第一段階である生産では、製品の品質を維持するために適切な低温処理が行われます。農産物、水産物、畜産物など、それぞれの特性に応じた温度管理が必要です。例えば、野菜や果物などの青果は、収穫後すぐに「予冷」を行い、低温環境で保管することで鮮度を維持します。一方、肉や魚といった生鮮食品は、急速冷凍機を用いて短時間で冷凍処理を施し、品質の劣化を最小限に抑えます。こうした初期の温度管理が適切に行われることで、次の加工・流通段階においても高い品質が維持されます。
加工
加工の段階では、品質を保ちながら安全性を確保するための処理が施されます。食品の場合、加熱処理や殺菌処理を経た後、密閉包装を行い、適切な温度で保管されます。特に冷蔵・冷凍食品は、加工時点での温度管理がその後の品質を左右するといわれています。また、医薬品など生命に大きく関わる場合も同様で、製剤や充填、包装などの工程を経て、厳格な温度管理の下で保管されます。こうした適切な加工処理により、製品は安全かつ高品質な状態で次の流通段階へと移行します。
物流
物流の段階では、生産地から消費地へ製品を低温のまま輸送することが求められます。冷蔵・冷凍トラック、航空機、船舶など、輸送手段に応じた適切な温度管理が行われます。輸送中は、冷蔵・冷凍倉庫を活用し、積み替え時の温度変化を最小限に抑えることが重要です。また、輸送時間を短縮し、製品の劣化を防ぐために、最適なルート選択も欠かせません。物流段階における管理の精度が、消費者の手元に届くまでの品質を左右するため、綿密な温度監視と迅速な輸送が求められます。
販売
販売段階では、消費者に渡るまでの間も適切な温度管理が継続されます。スーパーマーケットやコンビニエンスストアでは、冷蔵・冷凍ショーケースを活用し、製品を最適な温度で陳列します。また、陳列方法や管理体制も重要であり、一定の温度を維持するためのシステムが導入されています。消費者が購入した後も、適切な温度を保つことが求められるため、できるだけ速やかに冷蔵庫や冷凍庫で保管することが推奨されます。販売の現場での管理が適切であればあるほど、消費者はより良い状態の製品を手にすることができます。
消費
最後の消費段階では、製品を安全に使用・摂取するための適切な管理が求められます。特に冷凍食品を調理する際には、適切な方法で解凍することが重要です。例えば、室温での解凍は品質劣化や食中毒のリスクを伴うため、冷蔵庫内での緩やかな解凍が推奨されます。また、開封後の食品は、再冷凍による品質の劣化を防ぐため、できるだけ早めに消費することが望ましいでしょう。冷蔵庫や冷凍庫での保存状態を適切に管理することで、食品の安全性と美味しさを維持できます。
コールドチェーンのメリット・重要性
冒頭にも説明した通り、コールドチェーンが整備されたことで私たちの生活は一変しました。では、具体的にはどのような場面でその役割を発揮しているのでしょうか?
コールドチェーンの主な目的は、低温状態を維持することによって各商品の品質を一定に保つことです。これまでの輸送方法といえば通常のトラックで屋外の倉庫などに常温で運搬されるのが一般的でしたが、クール便や冷凍・冷蔵倉庫の拡大によって低温流通が実現しました。これにより、鮮度を保ったまま消費者の元へ様々な商品を送ることができるようになりました。
また、低温状態を長期化させることで、各商品のロスも削減できます。たとえば生鮮食品であれば低温管理によって雑菌の繁殖や鮮度の劣化を防ぎ、店舗でより長い期間販売できるため、賞味期限切れによる廃棄の減少に繋がります。
さらに、コールドチェーンは商品の販路拡大にも一役買っています。従来の輸送形態では各地に中継地点となる物流の拠点が必要であり、品質維持の観点から遠方へのダイレクト輸送が困難でした。そのため、低温管理が必要な商品の輸送エリアは基本的には出荷地の周辺数十キロに限られていました。
コールドチェーンによりこうした商品の長距離輸送が可能になったことで、出荷地から遠く離れた全国各地へ商品を届けることが可能となりました。一部地域でしか販売されていなかった商品や、鮮度を売りにした商品が遠方からでも購入できるようになり、経済圏を大幅に拡大させました。
コールドチェーンの影響は、物流だけに留まりません。医薬品や血液パックなどの温度管理にも必須の技術となっています。特にコロナ禍では、ワクチンの低温管理が重要な政策として各国で認識され、一気にコールドチェーンの普及が進んだともいわれています。
このように、コールドチェーンは物流業界以外にも、様々な業界へ影響を及ぼす重要なテーマとなっています。
コールドチェーンの課題
いまや現代人の生活になくてはならないコールドチェーンですが、いくつかの課題も露見しています。なかでも、特に問題視されているのが、温度モニタリングにおける人為的なミスです。
鮮度や品質を担保する技術であるコールドチェーンでは、一貫した温度管理が絶対条件です。当然ながら、各商品は生産から消費者の手に届くまで、一定の温度が維持されているか定期的にチェックを行います。
一方で現行のコールドチェーン管理は、定期的な温度モニタリングと手作業による記録管理に頼ってきたため、人の手によるミスや不正が起こりやすく、リアルタイムでの温度管理や可視性にも欠けていました。
人為的ミスが原因で空調が万全に機能していなければ品質の維持は担保できず、リアルタイムでモニタリングできなければ、スケジュールが少しずれるだけで想定外に商品を常温下に晒されることもあるかもしれません。
また、ミスではなく意図的に低温管理が怠られる可能性もあります。ベトナムなどの東南アジア諸国では、ドライバーの賃金体系が運賃の中から会社利益を含む必要経費を除いた金額が収入となるケースがあります。したがって、少しでもガソリン代を節約するために、定期的なエンジン停止を行っているドライバーも少なくないのです。商品の品質だけでなく、誠実なドライバーが損をすることにもなってしまいます。
リアルタイムかつシステマチックに監視を行わなければ、上記のようなミスや不正を解決することはできないでしょう。
コールドチェーンの課題解決にブロックチェーンが注目されている
物流業界では前述のような課題に対し、ITの世界から様々な技術を活用することで解題解決を図る取り組みが見られます。その中でも、特に期待されているのがブロックチェーンです。
「ブロックチェーン」という言葉は耳にする機会が増えていますが、具体的にどのような技術なのか、イメージが湧かない方も多いかもしれません。そこでまずは、この技術の概要について見ていきましょう。
ブロックチェーン=管理者不要でデータを安全に記録・共有する技術
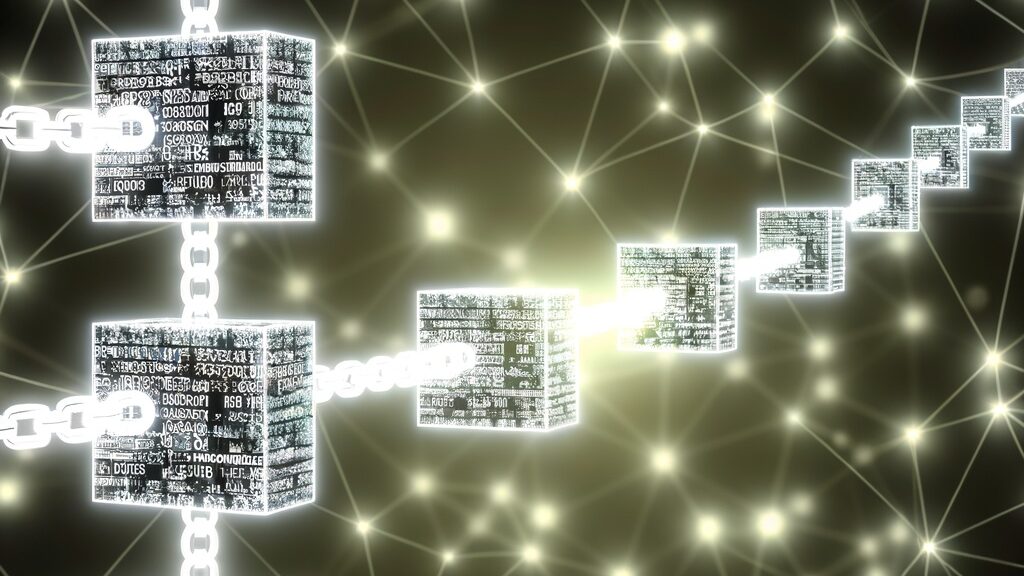
ブロックチェーンは、サトシ・ナカモトと名乗る人物が2008年に発表した暗号資産「ビットコイン」の中核技術として誕生しました。取引データを暗号技術によってブロックという単位にまとめ、それらを鎖のようにつなげることで正確な取引履歴を維持しようとする技術です。
ブロックチェーンはデータベースの一種ですが、そのデータ管理方法は従来のデータベースとは大きく異なります。従来の中央集権的なデータベースでは、全てのデータが中央のサーバーに保存されるため、サーバー障害やハッキングに弱いという課題がありました。一方、ブロックチェーンは各ノード(ネットワークに参加するデバイスやコンピュータ)がデータのコピーを持ち、分散して保存します。そのため、サーバー障害が起こりにくく、ハッキングにも強いシステムといえます。
また、ブロックチェーンでは、ハッシュ値と呼ばれる関数によっても高いセキュリティ性能を実現しています。ハッシュ値とは、あるデータをハッシュ関数というアルゴリズムによって変換された不規則な文字列のことで、データが少しでも変わると全く異なるハッシュ値が生成されます。新しいブロックを生成する際には必ず前のブロックのハッシュ値が記録されるため、誰かが改ざんを試みると、それ以降のブロックのハッシュ値を全て再計算する必要があり、改ざんが非常に困難な仕組みとなっています。
さらに、ブロックチェーンでは、マイニングという作業を通じて、取引情報のチェックと承認を行う仕組み(コンセンサスアルゴリズム)を持っています。マイニングとは、コンピュータを使ってハッシュ関数にランダムな値を代入する計算を繰り返し、ある特定の条件を満たす正しい値(ナンス)を見つけ出す作業のことで、最初にマイニングに成功した人に新しいブロックを追加する権利が与えられます。
このように、ブロックチェーンは分散管理、ハッシュ値、マイニングなどの技術を組み合わせることで、データの改ざんや消失に対する高い耐性を持ち、管理者不在でもデータが共有できる仕組みを実現しています。
詳しくは以下の記事でも解説しています。
ブロックチェーンがコールドチェーンをどう変える?
データの真正性が担保される
従来のデータベースでは、企業や個人がすでに記録された管理履歴を改ざんすることは(知識があれば)容易でした。特に管理者による内部不正を防いだり検知するのは非常に困難です。一方のブロックチェーンは「ハッシュ」や「ナンス」、「公開鍵暗号方式」といった様々な要素によって、管理者も含めて改ざんすることが著しく難しいデータベースになっています。
したがって、ドライバーや検温員といった各作業者のモラルに委ねられていた温度管理を厳格に行うことができます。これにより、理論上可能であった商品の品質の維持が内実ともに可能になります。
また、データが常に正しいのであれば、仮に冷蔵・冷凍機器が故障していて品質に問題が生じた場合も、すぐにその原因となっている地点を特定することができます。自動車や家電などリコールが発生しやすい製品の製造ラインでは、比較的こうしたデータの取得を行っていることが多いです。しかしながら、生鮮食品などの分野ではこうしたサプライチェーンの管理が徹底されているケースは多くありません。こうしたいわゆる「トレーサビリティ」の分野でもすぐに問題の根源を特定できるというのは新たな価値になりうるでしょう。
チェーン全体でデータへアクセスできる
ブロックチェーンでは分散してデータの管理を行います。したがって、従来のデータベースのように場合によってはデータの改ざんが可能な特定特権的なの管理者を持ちません。チェーンの参加者全員がデータへアクセスすることも可能です。こうした特徴を活かして、チェーン全体で当事者意識を持って品質の管理に取り組むことができます。
たとえば、生産の段階で低温管理に最大限配慮している企業があるとします。しかし、その商品を配送するフェーズで温度管理を徹底しなければ、いくら生産者が努力したところで品質は向上しないままです。それどころか、現状のデータ管理では生産者は生産、配送業者は輸送のデータをそれぞれが管理しているために、生産者は原因が分からずじまいになってしまいます。
一方でブロックチェーンを導入しているコールドチェーンであれば、自社の担当範囲以外でも商品の情報を追跡できます。したがって、どこのフェーズが品質を低下させているかを相互に監視・確認し合うことで、品質を一定に管理できるような環境を構築できます。
これはブロックチェーン技術を使った貿易プラットフォームや不動産プラットフォームが、売り手と買い手以外のどの関与者の間でどのような情報のやりとりがおこなわれているかを全プレーヤーで確認できるのと、構造は同じです。
面倒な確認も不要で正当な取引が可能
ブロックチェーンにはもう一つ、従来のデータベースにはない武器があります。それが「スマートコントラクト」です。スマートコントラクトとは、事前に決めた条件に基づいて、それを満たした場合には自動的に契約が実行されるという仕組みのことです。
このスマートコントラクトを活用すれば、正当な取引が可能になります。これまでの取引では、物流段階での温度管理が実際にされているかどうかはわかりませんでした。そのため「されているだろう」の暗黙の了解のもと、物流業者の信用において取引がされていました。
スマートコントラクトを用いれば、条件に低温管理(◯度以下で配送が行われた)を設定することで、条件を満たしている商品に対して自動的に受け入れを行えるため、両者にとってフェアな取引を瞬時に完了できます。時間や手間をかけることなく商取引が行えるため、時間をより有効に使うことができるでしょう。
また、万が一契約温度を下回ってしまったことが検知されたら、スマートコントラクトを活用することで自動で追加発注を掛けられます。追加発注の確認待ちによる時間のロスを大幅に削減することも可能になるかもしません。
RFIDによって、さらにブロックチェーンの可能性は広がっている
コールドチェーンで重要な検討事項となるのが、データの取得点です。データの管理をブロックチェーンで行うことで真正性を担保したとしても、効率よくデータの連携をすることができなければブロックチェーンの導入メリットは限られたものになってしまいます。
これまでの多くのコールドチェーンでは「データロガー」と呼ばれる温度管理システムが用いられており、各ロガーから得た情報を事後管理するやり方が一般的でした。しかし、データロガーを用いた方法ではリアルタイムの状況に合わせた温度管理ができないばかりか、コストの観点からも適用できるのはトラックやコンテナ輸送のような商品が集積された管理形態に限定されてしまいます。そのため、コールドチェーンで求められる個別商品単位でのきめ細かな管理ニーズに応えることができませんでした。
この課題を解決するために、近年、RFIDと呼ばれるツールが利用され始めています。RFIDとは「Radio Frequency Identification」の略で、近距離の無線通信を用いてID情報などのデータを記録した専用タグと非接触かつ自動で情報をやりとりするシステムのことです。
RFIDの最大の特徴は、遮蔽物・距離に強いこと、そして複数のタグを一括読取できることです。バーコードやQRコードのようにカメラを用いて読み取るシステムとは異なり、RFIDは電波を用いて情報をスキャンします。そのため、離れていたり、他のものと重なっている場合でも、安定して読み取ることが可能です。段ボールなど箱の中に入っているタグの情報も読み取ることができます。
さらに、ICタグにはラベルタイプのものやプラスチックなどのハードケースに包まれたもの、交通ICのように「かざす」動作で通信するNFCタイプのものなど様々な種類が存在します。サービスや商品の性質、読み取りシーンに合わせたタグを扱うことができるため、導入のハードルも一気に下がるでしょう。
こうしたツールを活用することで、新しいコールドチェーンでは、商品ごとの個別情報を一元管理し、各商品に個別最適化された温度管理を行うシステム(つまりはIoTシステム)が実現するといわれています。
RFIDとブロックチェーンを組み合わせることで、安全かつ簡易化された温度データ管理の時代が訪れるでしょう。受発注・決済・所有権移転も含めたトレーサビリティをリアルタイムかつ関係各社で一元管理できるようになるため、サプライチェーンマネジメントを大きく飛躍させると期待されています。
ブロックチェーン×コールドチェーンの事例
2024年現在、流通業界ではブロックチェーンをはじめとする先進技術によってプロセスイノベーションを起こすべく、各社で大規模な技術開発や実証実験が行われています。ここからは、ブロックチェーンとコールドチェーンを掛け合わせた事例についてご紹介します。
東京都立産業技術研究センター
東京都立産業技術研究センターはモノコトデザイン株式会社、ビヨンドブロックチェーン株式会社と共同で、ブロックチェーン技術を使ったセキュアなオープンプラットフォームを開発しています(2023年5月より一部機能の運用開始)。
このプラットフォームでは、POS(販売時点情報管理)やWMS(倉庫管理システム)など、すでに使われている複数のシステムとの連携しながら、コンタミネーション(異物混入)の防止や食品衛生規格などのトレーサビリティにも対応しています。
データの取得にはRFIDを採用しており、端末で収集したデータを、簡単に物流サーバへアップロードすることが可能です。また、配送ボックスは内部に開封検知機能と温度センサ機能を有しており、配送ボックスの外側にRFIDタグを貼付して、輸送履歴をトレースします。したがって、温度管理に加えて中身の入れ替えなどがないことを検出できる仕組みになっています。
同サービスはデータ改ざんの防止に利用されるブロックチェーンを使うことにより、今後ますます複雑化が予想される物流システムを透明化し、安全性の担保が必要となる商品のトレーサビリティデータを記録していくということです。
北京市
2020年11月、中国の首都である北京市はブロックチェーンを活用したコールドチェーンプラットフォームである「北京冷鏈」をスタートさせました。これにより、消費者が冷凍食品を直接トレースできるようになりました。
契機となったのは同年の6月に、北京の食品卸売市場で輸入サーモンをさばいたまな板からコロナウイルスが検出されたことでした。感染の中心地である中国において、このニュースは大々的に報じられ、スーパーの店頭からはサーモンの姿が消えて輸入も一時停止されました。
こうした騒動を受け、「コールドチェーン導入」は、感染防止におけるキーワードに浮上しました。実は、先進国では食品物流の90%はコールドチェーンを経由しているのに対し、中国の普及率は極めて低く、70%は常温で管理されています。アイスクリームさえ毛布などに包んで常温で配送することもあるそうで、コールドチェーンの導入が喫緊の課題です。
そういった背景のなかで、公的な研究機関である微芯区塊鏈研究院が中心となって「北京冷鏈」の開発に成功しています。Wechat、 Alipayといったアプリを通して、当該商品の二次元コードをスキャンするだけで、商品履歴を確認できる仕組みです。
この国家的プロジェクトにおいても、ブロックチェーンはコールドチェーン食品の生産元、流通、倉庫保管、消費などの各段階のデータの改ざんを防ぐ技術として採用されています。
IBM × eProvenance
ブロックチェーンの社会実装を積極的に行っているIBM社も、もちろんコールドチェーン分野に進出しています。同社はワインの出荷分析を行っているeProvenanceと共同でブロックチェーンプラットフォーム VinAssureの立ち上げを行いました。
ワインの保管と輸送中の温度条件は、品質に重大な影響を与えます。そのため、他の高級酒が常温でも保存がきくのに対して高級ワインはワインセラーでの保管が必須です。また、眠らせれば眠らせるだけ深みや価値が出てくるワインでは、24時間365日常に低温で管理される必要があります。
VinAssure は、AIやブロックチェーン、クラウドといった様々な先端テクノロジーが活用されているBlockchain Transparent Supplyをカスタマイズすることで、ワインに関する製造・管理のデータを追跡することが可能です。
プラットフォームの参加者はワインボトルにあるQR コードを読み取ることでサプライチェーン情報にアクセスでき、製品の認証基準、品質、オーガニック関連情報などを確認することができます。また、消費者だけでなく、ワインメーカーも生産に費やされた細心の注意を反映しているという、セルフブランディングにも活用することができます。
VinAssure にはすでに米国に本拠を置く複数のワインメーカーも参加しており、今後もサービスの拡大が期待されます。
日立製作所
東南アジアでは、近年の経済発展とともに高所得者層が増加し、品質管理された食品への要求が高まっています。しかしその一方で、コールドチェーンが未発達なことにより品質管理された食品が十分に消費者に提供されていません。こうした状況をコールドチェーン物流によって改革しようという試みが、日立製作所FCPF(Food Chain Platform、フードチェーンプラットフォーム)構想です。
本プロジェクトでは、同社が開発した温度検知ラベルを用いることで、商品ごとに個別に、しかも安価に取り付けることができるため、輸送単位を限定することなく、生産者から消費者までのすべての工程で適切な温度管理を行うことができるとされています。
同社は、「FCPFは温度検知ラベルのほかに、ブロックチェーン、ロジスティクス管理、画像診断/AI(Artificial Intelligence)、保冷ボックス、鮮度・熟成度シミュレータなど複数の日立の強み技術を活用し、食品の品質管理、トレーサビリティ、ダイナミックマッチング、物流指示などのサービスを提供することで、生産、卸、物流、小売り、さまざまなステークホルダーの要求に応じた価値を提供する」ことで、「従来よりも安価なコストできめ細やかな温度管理」を実現するとしています。
本プロジェクトは、センシングデバイスとIoT技術、AI、そしてブロックチェーンを組み合わせることで、コールドチェーンの課題をDXで解決しようとする好例だといえるでしょう。
まとめ
本記事では、ブロックチェーンがコールドチェーンに対してどのような貢献ができるのかについてご紹介しました。コールドチェーンは現代の物流を支える重要な技術であり、今後ますます拡大が予想されます。一方で、導入にあたっては、仲卸業者や輸送業者などサプライチェーンに関わる人たちに理解や協力をしてもらう必要もあるかと思います。
従来のデータ管理では、かえって仲卸業者や輸送業者の手間が増えてしまい、なかなか理解や協力を得られないでしょう。ブロックチェーンによって安全かつ迅速なデータ管理を実現することで、こういった社内外の調整業務もスムーズに進むことでしょう。
トレードログ株式会社では、非金融領域におけるビジネスへのブロックチェーン導入を支援しています。新規事業のアイデア創出から現状のビジネス課題の解決に至るまで、包括的な支援が可能です。自社のコールドチェーンについて少しでもお悩みがございましたら、是非オンライン上で30〜60分程度の面談をさせていただければと思いますので、お問い合わせください。
〈関連リンク〉
COLD X NETWORK|ケース単位からパレット複数まで、預けたい期間、必要なスペースだけ利用できる冷凍保管サービスを展開
LOGI FLAG|賃貸型冷凍冷蔵倉庫をはじめとして、環境に配慮した冷却設備や自動化設備を導入した先進的な物流施設を提供します
-1.png)
