イスラム教の戒律に則って調理・製造された製品であることを示す「ハラル認証」。グローバル化の進展に伴い、近年国内でも脚光を浴びる機会も多くなってきました。本記事では、そもそもハラルとは一体何なのか、相次ぐ「偽装ハラル」は何が問題なのか、解決策となるブロックチェーン技術についても解説します!
ハラルとはどういうものなのか?
ハラルは、ムスリム(イスラム教徒)の行動指針となる基準の一つ
「ハラル(Halal)」とは、イスラム法において「合法」「許される」という意味のアラビア語です。イスラム教の教えでは、神が創造したものはすべてハラル(許されること)であり、それ以外のものは「ハラム(Halam)」として禁じられており、イスラム教徒のあらゆる行動や全ての物はこの「ハラル/ハラム」を基準に判断されます。
ハラルは聖典であるコーランや預言者ムハンマドの言行録であるハディースに規定されています。
ハラルフードとは、イスラムの教えで食べてよいとされる食べ物
イスラム教では、食べ物に関しても「食べてもよいもの」と「食べてはいけないもの」が細かく定められています。そのイスラム教の教えで食べてよいとされている食べ物を「ハラルフード」と呼びます。
イスラム教徒は豚肉やアルコール等の摂取が認められていないというのはご存じの方も多いかと思います。しかし、製造工程においてもイスラムの戒律に則った方法で処理される必要があります。具体的な例としては、アルコールが添加されている味噌や醤油などの調味料やムスリム以外によって処理された食肉、遺伝子組み換えによって栽培された植物なども摂取が厳しく禁じられています。
このようなイスラム教の独自の基準にクリアした、いわゆる「ハラルフード」のみが、ムスリムが摂取を許されている食品となります。
日本でもハラルへの関心が高まっている
一見すると複雑なルールでもあるハラルですが、近年、国内でもその存在が広く知られるようになっています。それは、イスラム教が世界人口の約4分の1を占める世界的な宗教であり、インバウンド需要に対応する日本の各業界においてハラルは避けては通れないテーマだからです。
とくに飲食業界においてはハラルフードを取り扱う店舗も首都圏を中心に現れつつあり、観光庁も「訪日ムスリム旅行者対応のためのアクション・プラン」を発表するなど、訪日ムスリムに対する食や礼拝への配慮が高まっています。
また、イスラム教徒は今後さらに増加するという予測も立てられています。米世論調査機関ピュー・リサーチ・センターの予測によると、イスラム教は増加のペースが最も速く、信者の数は2050年までに27億6000万人に増える見通しだといいます。これは同年の世界人口予測の約3割に値する数字であり、それだけイスラム教徒が急増するということは、ハラルフード市場も拡大していくものと推測されます。
宗教への関心が薄い私たち日本人であっても、ビジネスやサービスのうえでは全くの無関心というわけにはいかなさそうです。
ハラル認証によってムスリムは安心して食品を選択できる
ハラル認証とは?
ハラル認証とは、イスラム教の戒律に則って調理・製造された製品であることを示すシステムです。「イスラム世界で禁じられるもの」すなわち「ハラムなもの」が、製品やサービスに含まれていないことを客観的な証拠をもって確認し、基準をクリアしたものに「ハラル認証マーク」が付与される仕組みとなっています。
食品加工技術や流通が発達するにつれ、一般的なイスラム教信者の消費者には、目の前の商品がハラルなのかそうでないのかの判別が必要となりました。そこで宗教と食品科学の2つの面から、その商品がハラルであることを認証機関が保証するハラル認証の制度が誕生しました。
「イスラム的に許容されているか」の判断を中立的な立場の第三者機関が審査することで、企業側も安心して製品を製造・輸出することにつながります。この役割を担うものとして、ハラル認証機関の存在は近年益々重要視されてきています。
東南アジアに多いハラル認証
現在、ハラル認証の製品や店舗は、イスラム教徒人口の多い東南アジアを中心に普及しています。特に高経済成長中であるマレーシア、シンガポール、インドネシアといった国々では富裕層やアッパーミドルのムスリムが増加しつつあり、こうした国々への輸出ではハラル認証が有効なプロモーションの一つとなっています。
一般的な感覚からすると、「サウジアラビアなどの中東で需要があるのでは?」と思うかもしれませんが、こうした国々ではハラル認証がされた製品はあまり流通していません。これは中東の国々ではイスラム教が国教として制定されており、「すべてがハラル」が前提となっているためです。
日本の輸出先はアジア圏が大半を占めているため、東南アジアでハラル認証の導入が進んでいるというのは重要なトピックといえるでしょう。
日本企業もハラル認証を取得している
意識せずに生活していると全く気づかないかと思いますが、実は日本企業がハラル認証を取得しているケースもたくさんあります。日本国内に暮らすイスラム教徒は約20万人いるといわれており、そうしたニーズに応えるべく、大手企業を中心にハラルフードの取り扱いを行っている企業が生まれているのです。
日本においてハラル認証を受け、公表している企業は日本ハラール協会のサイト上で公開されています。
ハラルへの取り組み事例
LIFE SCHOOL 桐ケ丘 こどものもり
東京都北区のとある保育所では、ハラル認証の取り組みが行われています。「LIFE SCHOOL 桐ケ丘 こどものもり」では、認可保育所としては全国初のハラル認証を取得し、園内の調理場でイスラム教徒用の給食を提供しています。
認証を取得するにあたって、栄養士がハラルフードに関する講習を受けて専門的な知識を学んだほか、専用の調理器具も用意するなど内部の仕組みを整備しました。また、処理場で処理された鶏肉を使ったタンドリーチキンなど、食事を許されている食材についてもしっかりとイスラム法の規定に則っているものを使用する体制へと食材の供給網にも工夫をしています。
日本の園児用メニューと見た目も同じにすることで、園児同士でのトラブルや保護者からのクレームもなく、園内に十数人在籍しているバングラデシュ国籍の園児も安心して給食を楽しんでいるようです。
現在はハラルへの対応がなされている保育園はあまり多くはありませんが、こうした先進事例を通して今後教育のシーンでもハラルフードへの理解が増進していくことと思われます。
神戸ビーフ
海外で人気が高まっている高級和牛の「神戸ビーフ」もハラルへの対応を始めました。富裕層の多い中東での消費拡大を狙い、ハラル認証の基準を満たす食肉施設で処理された「神戸ビーフ」がサウジアラビアに輸出されています。
サウジアラビアは、厳格にイスラム法を適用している国家の一つです。近年、女性の社会進出や政治参加の機会も増えつつありますが、それでもなおコーランを法源としており、近代的価値観に抵触する規範も多くあります。そんなサウジアラビアではもちろん、牛肉は宗教上のルールで定められた方法で処理されたハラルであるものしか食べることができません。
そうした国に対しても日本産和牛のおいしさを伝えるべく、兵庫県内で神戸ビーフを産出していると畜場が「ハラール神戸牛」への生産に取り組みました。ハラルと畜専用の設備を設け、非ハラルの肉等と完全に分離されたラインを確保することで、安心のと畜環境を用意しています。
また、加工プロセスや保管場所についてもハラルではないものと混ざることは厳禁で、ハラル専用の冷凍庫を使用したり、消毒もアルコールが使えないため熱湯で行うなど様々な工夫がなされています。
こうした各工程での努力によって、肉質を損なうことなく神戸ビーフの味を楽しんでもらうことができます。ムスリムにも余すことなく日本の食文化も味わってもらい、世界に日本食のおいしさを広めるうえでもハラル認証への取り組みは欠かすことができない存在でしょう。
近年増加している「偽装ハラル」
偽装ハラルとは?
イスラム教徒にとって生活の肝となっているハラルですが、近年問題となっているのが「偽装ハラル」です。偽装ハラルとは、ハラルでないにも関わらずハラルであると偽装して流通している食品のことを指します。
前述のハラル認証の制度によって、ハラルフードにはハラルであることを証明するロゴが貼り付けられていることがあります。ムスリムの消費者は、表示された認証マークによってその製品が厳しい審査手続きを経て、安全に消費できると証明されていると確認することができます。
しかし、この表示は業界全体として統一されたものではなく、発行団体によってそれぞれ異なるロゴを掲げている場合もあります。日本でも30以上のハラル認証機関が存在するといわれており、これらをすべて記憶しておくのは日常生活では実質的に不可能でしょう。
こうした新興かつ曖昧なマーケットを悪用した業者がハラルでない食品に対してハラルの認証マークをつけて販売することで不当に利益を得ているというのが、偽装ハラル問題の正体です。この問題は世界的にも深刻な話題であり、信仰人口が十数億人に上るとされているイスラム教ではその被害者・被害額はとてつもない規模となっていることが窺い知れます。
イスラム教徒にとっての偽装ハラル
イスラム教徒にとって偽装ハラルは文字通りの「死活問題」になります。2024年現在、ハラルの認証を受けていない製品に関する詐称問題が相次いでいます。とくにタイのチュラロンコン大学の調査によって発覚した「偽装牛肉(牛の血に浸した豚肉を牛肉と偽って販売)」の問題は世界中のイスラム教徒に大きな衝撃を与えました。
過去には日本企業もハラル関連で「炎上」した事例もあります。2014年、大手菓子メーカーのブルボンでは人気ラインナップである「プチ」シリーズのコンソメ味にインドネシア語での原材料表示を貼り付けないまま、インドネシア国内で販売しました。
コンソメ味のポテトチップスには豚由来のエキスが使用されており、漢字の読める女子大生がSNSで拡散したことをきっかけに同製品は回収に追い込まれる騒ぎとなりました。インドネシアでは国民の9割近くがムスリムであり、この事件は私たち日本人とムスリムのハラルフードに対する認識の違いを体現する結果となりました。
インドネシアでは、2000年にも大手総合食品メーカーの味の素が豚由来の酵素を使用したとして、大きな話題となっています。当時は抗議活動も激しく行われ、現地法人の社長が逮捕される騒動となりました。このように、日本人の感覚では「ミス」というイメージであっても、イスラム圏ではこうしたミスは「イスラムの基準を満たした食品と偽った、消費者を欺いた」という「不正」の意味合いが強くなってしまいます。
厳格にコーランを遵守するムスリムに対してハラムである食品を提供することは、口にした本人のみならず宗教を侮辱することにもなりかねず、一企業・一個人の対応だけでは済まなくなる可能性もあるのです。
偽装ハラルに対抗する新たなテクノロジー
こういった偽装ハラル問題解決に向けて、ある新たな技術が注目されるようになりました。それが、近年ブランド製品の真贋証明などで利用されている「ブロックチェーン技術」です。ここからはブロックチェーン技術について簡単に解説します。
ブロックチェーン=管理者不要でデータを安全に記録・共有する技術
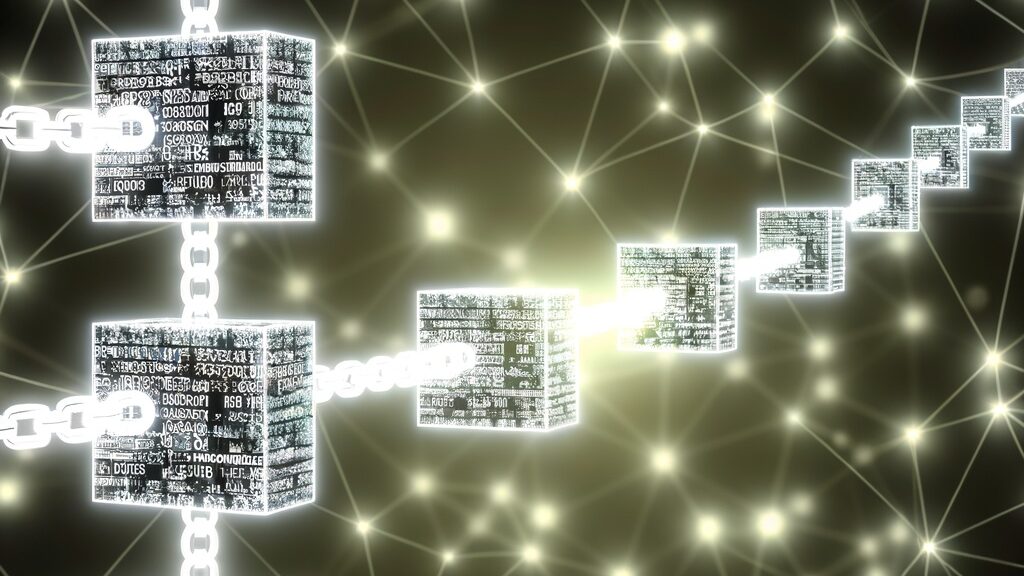
ブロックチェーンは、サトシ・ナカモトと名乗る人物が2008年に発表した暗号資産「ビットコイン」の中核技術として誕生しました。取引データを暗号技術によってブロックという単位にまとめ、それらを鎖のようにつなげることで正確な取引履歴を維持しようとする技術です。
ブロックチェーンはデータベースの一種ですが、そのデータ管理方法は従来のデータベースとは大きく異なります。従来の中央集権的なデータベースでは、全てのデータが中央のサーバーに保存されるため、サーバー障害やハッキングに弱いという課題がありました。一方、ブロックチェーンは各ノード(ネットワークに参加するデバイスやコンピュータ)がデータのコピーを持ち、分散して保存します。そのため、サーバー障害が起こりにくく、ハッキングにも強いシステムといえます。
また、ブロックチェーンでは、ハッシュ値と呼ばれる関数によっても高いセキュリティ性能を実現しています。ハッシュ値とは、あるデータをハッシュ関数というアルゴリズムによって変換された不規則な文字列のことで、データが少しでも変わると全く異なるハッシュ値が生成されます。新しいブロックを生成する際には必ず前のブロックのハッシュ値が記録されるため、誰かが改ざんを試みると、それ以降のブロックのハッシュ値を全て再計算する必要があり、改ざんが非常に困難な仕組みとなっています。
さらに、ブロックチェーンでは、マイニングという作業を通じて、取引情報のチェックと承認を行う仕組み(コンセンサスアルゴリズム)を持っています。マイニングとは、コンピュータを使ってハッシュ関数にランダムな値を代入する計算を繰り返し、ある特定の条件を満たす正しい値(ナンス)を見つけ出す作業のことで、最初にマイニングに成功した人に新しいブロックを追加する権利が与えられます。
このように、ブロックチェーンは分散管理、ハッシュ値、マイニングなどの技術を組み合わせることで、データの改ざんや消失に対する高い耐性を持ち、管理者不在でもデータが共有できる仕組みを実現しています。
詳しくは以下の記事でも解説しています。
ハラル認証へのブロックチェーン技術の利用
偽装ハラル問題が起こる原因の一つに「サプライチェーン全体をまとめる統一プラットフォームが不足している」ということが挙げられます。
ハラル認証は、本来であれば統一的な基準により判断されるべき制度です。しかし、サプライチェーン上のすべての利害関係者が、それぞれ異なるプロセスやシステムを利用しており、また手作業に頼っている部分が非常に多いのが実情です。
一方でブロックチェーンはデータの耐改ざん性に優れているデータベースであり、プロセスや企業の垣根を超えてデータ同士を鎖のようにつなげて共有することができます。データの真正性が担保された状態で一つのネットワーク全体としてデータが追跡できる仕組みを構築することで、各製品が正当なハラル認証であることを保証できるでしょう。
ブロックチェーン技術を使うことで、「サプライチェーン全体に透明性をもたらせながら、単一障害点化しない形で各セクションを統一しうるプラットフォーム」が実現できます。様々な製品の出所を追跡することで、仮に製品に関する情報が偽装されたとしても、もともとの生産地や生産状態を追跡していけば認証が取れるようになります。
また、ブロックチェーン技術のハラル認証への利用は、食品偽装防止に留まりません。医薬品、化粧品、ムスリムファッションの分野でもブロックチェーン技術の重要性が認知されつつあります。
ハラル商品全般に対してもこのテクノロジーを適用すれば、ハラルの市場認知度を食品業界の他の認証(例えば有機など)に匹敵するレベルまで高めることができます。冒頭にも述べたように、ハラル製品の市場規模は世界の人口の4分の1近くにものぼります。ブロックチェーン技術は偽装防止の枠を超え、ハラル市場の様々なコンプライアンスに革命的な進化を与えるでしょう。
ハラル×ブロックチェーンの事例
Halal Chain
現在では、ブロックチェーンを活用してハラル市場に参入するプロジェクトも増えつつあります。ハラル産業製品のトレーサビリティに特化したブロックチェーン技術をベースとする「ハラールチェーン(Halal Chain)」はその最たる事例でしょう。
ハラル認証を導入する際には、システムの不統一性や製品情報の不正確性、原材料に対する厳格な管理の難しさなど様々なテーマが問題となります。Halal Chainではバリューチェーンのあらゆる情報を一元的に管理し、分散して保有するというある意味で二律背反的な概念を実現することで、これらの問題の解決を試みています。
Halal Chainはパブリックなブロックチェーンであり、製造、加工から提供までのサプライチェーン全ての台帳上の取引をトラッキングして検証可能です。このシステムはリアルタイムでの監視も可能であり、ハラル認証に関する多くのコンプライアンスに革命を起こすと期待されています。
この構想は国際イスラム経済センター(ICIE)とドバイ空港フリーゾーン局(DAFZA)によるデジタルチェーンプロジェクトで発表されており、今後、イスラム圏の他の国々でも同様のプロジェクトが立ち上がるかもしれません。
WhatsHalal
シンガポールを拠点とするスタートアップである「WhatsHalal」は、ハラル食品をブロックチェーンプラットフォームを通じて効率的に認証するサービスを展開しています。
インドネシアでは2021年2月に「ハラル製品保証の実施に関する政令」を公布しており、飲食品は2024年までに、化粧品などは2026年までにハラルであるか非ハラルであるかについての表示をパッケージに記載することを順次義務化しています。同規制の導入によって、自社製品のハラル対応を推進しようと奔走する企業は150万社以上にのぼるとみられます。
こうしたインドネシア国内の動きを受けて、ブロックチェーンを活用することでフードチェーン内のハラル食品の追跡システムを統合しているのがWhatsHalalです。現在のSCM(サプライチェーン・マネジメント)のシーンでは、農業従事者からメーカー、販売業者、消費者まで、サプライチェーン全体のすべての利害関係者をまとめる統一プラットフォームが不足しています。
しかし、WhatsHalalでは専任のコンサルタント(有料)によって自社サービスでトレーサビリティが必要となる箇所がピックアップされ、サプライチェーン全体で一括してハラルを管理することができます。
そのため、業者はもちろん、顧客もアプリを使ってハラルが保証された特定の業者からハラル食品を注文・配達してもらうことが可能です。バーコードをスキャンすることによってハラルの正当性を確認する仕組みは、ムスリムにとって生活の利便性を大きく向上させるでしょう。
まとめ
イスラム教人口の増加に伴い、今後日本にも観光客としてだけでなく、留学生や移住者なども増えていくことでしょう。今までのように異国の文化や異宗教の変わった風習としてハラルを特別視するのではなく、ヴィーガンメニューや糖質カット食品のように、食品選択の際のオプションとして当たり前に用意されている環境が訪れる日もそう遠くないはずです。イスラム教に限らず、グローバルな視点でさまざまな宗教や文化への理解を深めておきましょう。
トレードログ株式会社では、非金融分野のブロックチェーンに特化したサービスを展開しております。ブロックチェーンシステムの開発・運用だけでなく、上流工程である要件定義や設計フェーズから貴社のニーズに合わせた導入支援をおこなっております。
-1.png)
