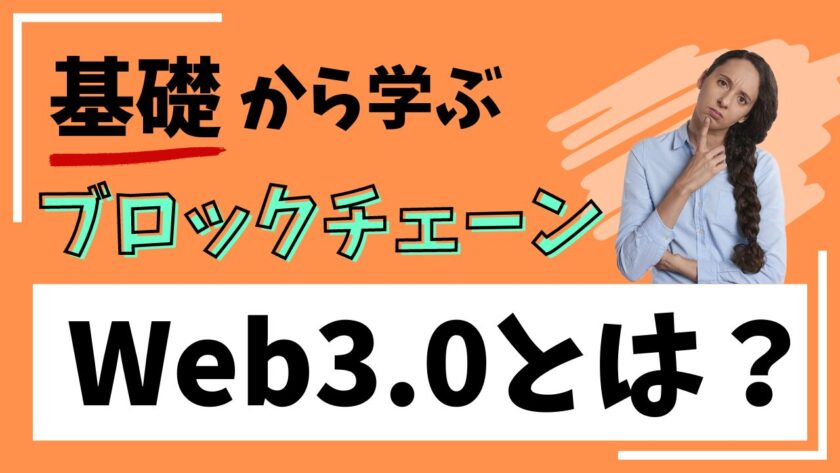2021年以降話題を集めている仮想通貨やNFT「Non-Fungible Token(非代替性トークン)」、メタバース(仮想現実)と共に、「Web 3.0」 という言葉を耳にする機会が増えてきました。Web3.0は別名「次世代のインターネット」とも呼ばれ、現時点でもっとも新しいインターネットの概念です。
本記事では、Web3.0に至るまでのWebの歴史を振り返った上で、Web3.0とは一体どういった概念なのか、またそのユースケースについて焦点を当てて解説していきます。
Web3.0とは?
Web3.0を解説するにあたり、これまでのWebがどのようにして進歩してきたかを以下の3つの時代に分けて解説します。
- Web1.0:1995年~(ホームページ時代)
- Web2.0:2005年~(SNS時代)
- Web3.0:これから(分散型インターネットの時代)
Web1.0(ホームページ時代)
Web1.0時代は、Yahoo!やGoogle、MSNサーチなどの検索エンジンが登場し始めた時期で、Webがまだ一方通行であった時代です。ウェブデザイナーのDarci DiNucci氏が1999年に、進化の段階を区別するためにWeb1.0とWeb2.0という呼び方を用いました。
ウェブサイトは1990年代初めに静的HTMLのページを利用して作られ、個人が「ホームページ」を持ち情報を発信する、という文化もこの時代から生まれました。ただし、インターネットの接続速度も非常に低速であり画像を1枚表示するだけでも時間がかかりました。
また、閲覧できる情報は情報作成者によってのみ管理されるため、閲覧ユーザーがデータを編集することはできません。こうした特徴からweb1.0は「一方向性の時代」とも呼ばれます。
Web2.0(SNS時代)

Web2.0時代になるとYouTube、Twitter、InstagramなどのSNSが登場し、誰もが発信者となりました。Web1.0時代が「一方向性の時代」とされたのに対し、Web2.0時代は様々な人との双方向の情報のやり取りができるようになったのです。
また、Google、Amazon、Facebook、AppleといったいわゆるGAFAと呼ばれるプラットフォームサービスが大きく躍進し、巨大テック企業となっていった時代でもあります。
一方で、個人情報がGAFAのような特定の企業へ集中することによる個人のプライバシー侵害の可能性が問題視されています。一部の大企業に集まる情報には、住所や年齢、性別など基本的な個人情報だけでなく、個人の嗜好や行動履歴までもが含まれ、それらが利用できる状態になっているからです。
また、プラットフォームの管理者が中心に存在している中央集権型のサービスでは、管理者が定めたルールに反してしまうとアカウントが凍結されたり、サービスを利用できなくなる可能性があります。政治的思惑によって発言や行動を制限されるおそれもあるでしょう。
さらに、中央集権型の情報管理はサイバー攻撃を受けやすく、多くのユーザーに影響を及ぼす危険性があるという点も指摘されています。
2018年には「Facebook」が5000万人超のユーザー情報を外部に流出。また、2019年には「Amazon」が他の利用者の氏名や住所、注文履歴などが誤表示されて約11万アカウントのプライバシーが流出。さらには2022年には、「Twitter」の利用者およそ2億3000万人分の個人情報が流出するなど、実際にセキュリティ上のリスクが露見した例もあります。
Web3.0(分散型インターネットの時代)
冒頭でも述べたように、Web3.0とは「次世代の分散型インターネット」のことを指します。さらにいうと、GAFAやその他巨大テック企業へ個人情報が集中している現状から、次世代テクノロジーを活用して情報を分散管理することで、巨大企業に情報が集中しない新しい形の情報管理のあり方として期待されているのがWeb3.0の概念です。
特定企業へ個人情報が集中していることによるリスクは前項でご説明した通りで、2021年以降、特定企業へ集中した情報を分散しようとする動きが活発化しています。管理者が存在しなくても、ユーザー同士でデータを管理したり、個人間でのコンテンツの売買や送金などが可能となっています。Web3.0 では、このように中央集権的なインターネットから脱却し、各参加者にデータや権限を分散する世界を目指しています。
この理念を実現するうえで、重要な鍵となっているのがブロックチェーン技術です。ブロックチェーン抜きにWeb3.0は語れないと言っても過言ではありません。ここからはブロックチェーンについて簡単におさらいします。
ブロックチェーンとは何か?
ブロックチェーン=正確な取引履歴を維持しようとする次世代データベース
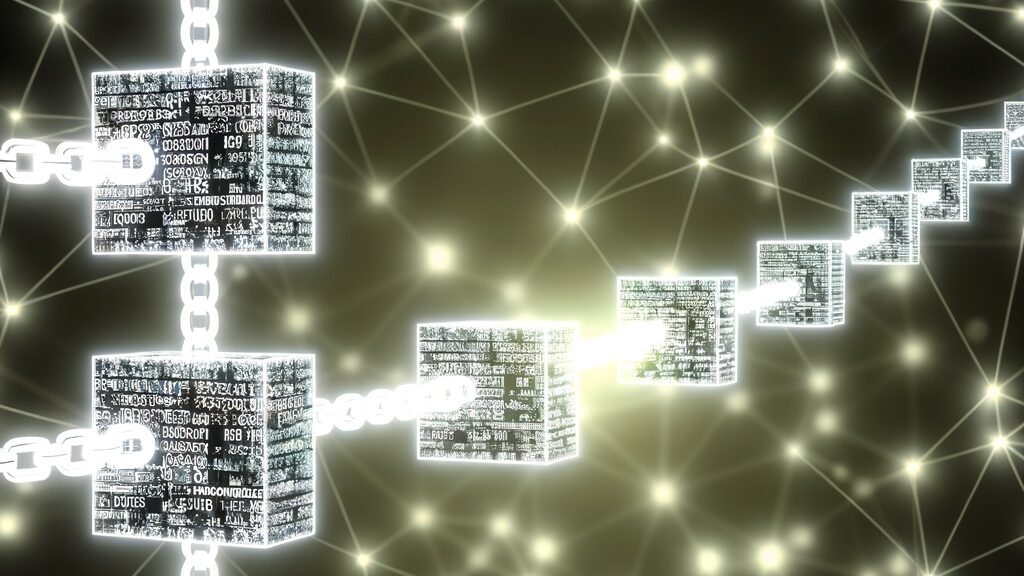
ブロックチェーンは、2008年にサトシ・ナカモトと呼ばれる謎の人物によって提唱された暗号資産「ビットコイン」の中核技術として誕生しました。
ブロックチェーンの定義には様々なものがありますが、噛み砕いていうと「取引データを暗号技術によってブロックという単位でまとめ、それらを1本の鎖のようにつなげることで正確な取引履歴を維持しようとする技術のこと」です。
取引データを集積・保管し、必要に応じて取り出せるようなシステムのことを一般に「データベース」といいますが、ブロックチェーンはそんなデータベースの一種です。その中でもとくにデータ管理手法に関する新しい形式やルールをもった技術となっています。
ブロックチェーンにおけるデータの保存・管理方法は、従来のデータベースとは大きく異なります。これまでの中央集権的なデータベースでは、全てのデータが中央のサーバーに保存される構造を持っています。したがって、サーバー障害や通信障害によるサービス停止に弱く、ハッキングにあった場合に、大量のデータ流出やデータの整合性がとれなくなる可能性があります。
これに対し、ブロックチェーンは各ノード(ネットワークに参加するデバイスやコンピュータ)がデータのコピーを持ち、分散して保存します。そのため、サーバー障害が起こりにくく、通信障害が発生したとしても正常に稼働しているノードだけでトランザクション(取引)が進むので、システム全体が停止することがありません。
また、データを管理している特定の機関が存在せず、権限が一箇所に集中していないので、ハッキングする場合には分散されたすべてのノードのデータにアクセスしなければいけません。そのため、外部からのハッキングに強いシステムといえます。
ブロックチェーンでは分散管理の他にも、ハッシュ値と呼ばれる関数によっても高いセキュリティ性能を実現しています。
ハッシュ値は、ハッシュ関数というアルゴリズムによって元のデータから求められる、一方向にしか変換できない不規則な文字列です。あるデータを何度ハッシュ化しても同じハッシュ値しか得られず、少しでもデータが変われば、それまでにあった値とは異なるハッシュ値が生成されるようになっています。
新しいブロックを生成する際には必ず前のブロックのハッシュ値が記録されるため、誰かが改ざんを試みてハッシュ値が変わると、それ以降のブロックのハッシュ値も再計算して辻褄を合わせる必要があります。その再計算の最中も新しいブロックはどんどん追加されていくため、データを書き換えたり削除するのには、強力なマシンパワーやそれを支える電力が必要となり、現実的にはとても難しい仕組みとなっています。
また、ナンスは「number used once」の略で、特定のハッシュ値を生成するために使われる使い捨ての数値です。ブロックチェーンでは使い捨ての32ビットのナンス値に応じて、後続するブロックで使用するハッシュ値が変化します。
コンピュータを使ってハッシュ関数にランダムなナンスを代入する計算を繰り返し、ある特定の条件を満たす正しいナンスを見つけ出します。この行為を「マイニング」といい、最初に正しいナンスを発見したマイナー(マイニングをする人)に新しいブロックを追加する権利が与えられます。ブロックチェーンではデータベースのような管理者を持たない代わりに、ノード間で取引情報をチェックして承認するメカニズム(コンセンサスアルゴリズム)を持っています。
このように中央的な管理者を介在せずに、データが共有できるので参加者の立場がフラット(=非中央集権)であるため、ブロックチェーンは別名「分散型台帳」とも呼ばれています。
こうしたブロックチェーンの「非中央集権性」によって、データの不正な書き換えや災害によるサーバーダウンなどに対する耐性が高く、安価なシステム利用コストやビザンチン耐性(欠陥のあるコンピュータがネットワーク上に一定数存在していてもシステム全体が正常に動き続ける)といったメリットが実現しています。
データの安全性や安価なコストは、様々な分野でブロックチェーンが注目・活用されている理由だといえるでしょう。
詳しくは以下の記事でも解説しています。
世界のGDPの10%がブロックチェーン基盤上に蓄積される?
「ブロックチェーン=ビットコイン」という認識は、すでに過去のものとなっていることはご存知でしょうか?一昔前(といっても2010年代ですが)までは、ブロックチェーンといえば、ビットコインを始めとする暗号資産(仮想通貨)を支える基幹技術の一つに過ぎませんでした。
それもそのはず、もともとブロックチェーンは、2008年に生まれたビットコインネットワークの副産物でしかなく、多くのビジネスパーソンからはFintechの一領域として認識されていました。しかし、ブロックチェーンの技術に対する理解が徐々に深まるにつれ、金融のみならず、物流・不動産・医療など、多種多様な産業での応用が進み始めました。
ブロックチェーンが単なるビットコインの補助技術ではなく、世界経済の重要な基盤として位置付けられるようになっている背景には、その技術の特性と多様な応用が挙げられます。
ブロックチェーンは分散型台帳技術であり、中央集権的な管理者が不在であるため、データの改ざんや不正アクセスを防ぐことができます。この特性は、金融だけでなく、物流、不動産、医療などの様々な産業で信頼性の高い取引や情報管理が求められる場面で大きな価値を持ちます。
そして、世界経済フォーラムによると、2025年までに世界のGDPの10%までがブロックチェーン上に蓄積されるようになるとの予測もなされるほどに、ブロックチェーンがこれまで以上に多くの産業で利用されるようになっています。たとえば、物流業界では製品の追跡や流通経路の透明化により、偽造品や盗難のリスクを減らすことができます。不動産業界では、不正な取引や不動産の二重売買を防止するために、土地登記や資産管理にブロックチェーンが活用されます。
これらの応用によって、ブロックチェーン技術は単なる金融の枠を超え、社会基盤の一部として不可欠な存在となっています。ブロックチェーンを単なる投機的な金融の一手法に過ぎないと見るか、それを次世代の社会基盤として位置付けるかによって、私たちの未来が大きく異なる可能性があります。
Web3.0は魔法の杖か?

Web3.0の時代では、情報管理のスタイルがブロックチェーン技術により非中央集権型となります。つまり、個人情報は特定の企業ではなくチェーンに参加したユーザーによって分散管理されます。また、サービスを提供する基盤は特定企業に限定されず、ユーザーひとりひとりが参加するネットワークがサービスを提供する基盤となるのです。
ユーザー同士が、ネットワーク上で互いのデータをチェックし合うということは、不正アクセスやデータの改ざんが非常に難しいことを意味します。特定企業が個人情報を握ることもなければ、情報漏洩によって多大な被害を被ることもありません。
このように、Web3.0の概念が実現すれば個人情報が分散管理され非中央集権型の情報管理スタイルとなり、不正アクセスや情報漏えい、データ改ざんのリスクが軽減し、Web2.0の問題点が解決できると考えられています。
一方で、Web3を持ち上げる誇大広告は目に余るものがあります。様々なメディアでまるでWeb3.0に移行することでWeb2.0ではできなかったことが一気に解決するかのようなような表現がなされています。しかし、そんなことはありません。
おおまかな定義としては「Web3.0=分散型インターネット」となりますが、この定義はとても抽象的で、なにか具体的で厳密な定義があるわけではありません。「Web3.0とは?」で検索してみると様々なサイトで定義がなされていると思いますが、おおよそ以下の要素が共通する認識としてある程度でしょう。
- 管理者がいない
- ブロックチェーンによるデータ管理
つまるところ、Web3.0とはこの2つの要素で構成されているに過ぎません。もちろん、管理者がいないことはブラックボックスの防止(開けたプラットフォーム)やデータの自己管理(閲覧範囲のカスタマイズ)が可能になりますし、ブロックチェーンによるデータ管理は耐改ざん性や耐災害性に優れています。
こうしたなにか明確な目的や課題に対してWeb3.0からアプローチをかけるのは有効ですが、メタバースやNFTなどの印象面だけに着目して、なにか目新しいシステムで話題性を呼びたいというプロジェクトはすぐに衰退していくでしょう。なぜなら、単に話題性だけならWeb3.0でなくても良く、むしろ決済に仮想通貨が用いられるWeb3.0は、新規参入者には敷居が高いからです。
また、目的設定に対しても「管理者は不要!中央集権は絶対悪!」というような意見が存在します。確かにデータが誰か一人(一企業)が独占しているというのは、プライバシー・セキュリティ的な観点に限っていえばあまり良いものではありません。
しかし、サービスによっては絶対的な管理者が存在するからこそ成り立っているものもあります。身近な例でいうとAmazonです。Amazonは消費者の購入フローの1から10まで(広告という意味では0から)すべてが完結できるプラットフォームです。
幅広い品揃えで全国に多数の倉庫を有し、莫大なユーザーを独占しているからこそああいったビジネスは成り立っており、管理のオペレーションが分散していないことで、24時間365日のサービス提供やその日買った商品がその日に届くということも可能なわけです。
もちろん、Amazonはこれによって莫大な手数料利益を得ていますが、私たちも以前よりも同じものを安く購入することができています。このような見方をすると絶対悪とはいえないのではないのでしょうか。
さらに、管理者がいないというのはすべての責任が(一次的には)自己責任だということです。法整備がされていないことも要因ですが、トラブルが起きたとしても誰も仲介には入ってくれないというわけです。
Web3.0の世界では完全に「P2P」のサービスが実現できるといわれていますが、Web2.0で個人間で取引するモデル、たとえば大手フリマアプリのメルカリでは、従来よりも取引の自由度やスピード感、無駄な手間などが解消された一方で、ユーザー間のトラブルも起きています。メルカリは事務局による手厚いサポートで事なきを得ていますが、Web3.0ではこの事務局的存在がいません。こうした問題をどう解決するのか、という問題は依然として残っています。
このように、Web3.0はインターネットの登場のような技術革新として捉えるのは正しくないことがお分かりいただけたでしょうか。Web3.0で万事解決、といった安直な考えは危険であり、魔法の杖ではなく、ビジネスの問題点を解決する一つのソリューションとして認識したほうがよいでしょう。
近年登場してきたWeb3.0のユースケース
NFT
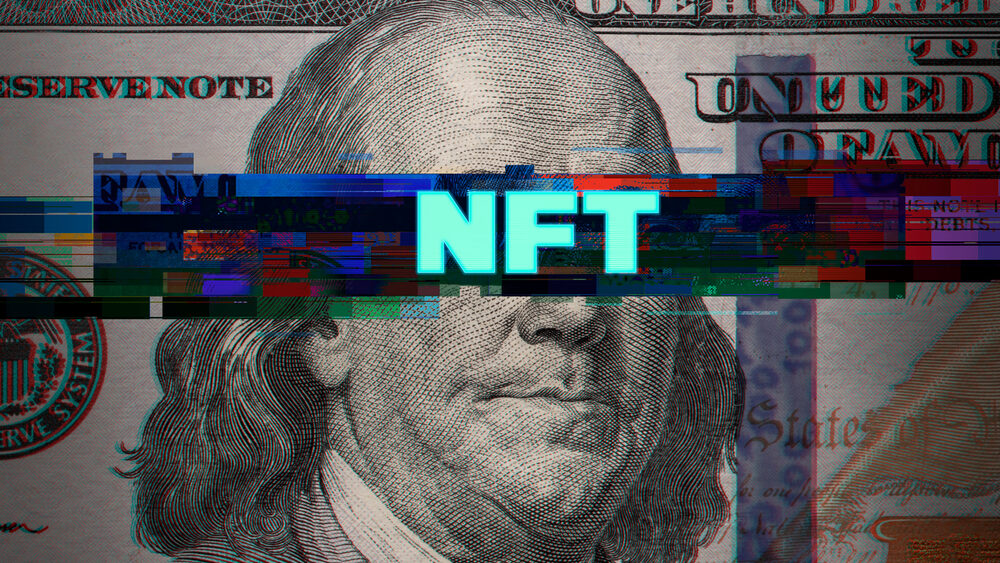
ブロックチェーン技術を基盤とするWeb3.0ですが、デジタルデータを分散管理する上で不可欠な事があります。それは、そのデジタルデータが本物である証明です。
管理者を置かずに全ての情報を分散管理するためには、やり取りされる情報の信頼性がこれまで以上に大切になってきます。出どころが分からない嘘の情報や不正にコピーされたデジタルデータが流通してしまうことは、管理者不在のWeb3.0においては致命的な欠陥となりえます。
しかし、従来のデジタルデータは簡単にコピーでき、本物とコピーの区別をつけることはほぼ不可能でした。ここで役に立つのがNFTです。
NFTを言葉の意味から紐解くと、NFT=「Non-Fungible Token」の略で、日本語にすると「非代替性トークン」となります。非代替性とは「替えが効かない」という意味で、NFTにおいてはブロックチェーン技術を採用することで、見た目だけではコピーされてしまう可能性のあるコンテンツに、固有の価値を保証しています。
世の中のあらゆるモノは大きく2つに分けられます。それは「替えが効くもの」と「替えが効かないもの」です。前述した「NFT=非代替性トークン」は文字通り後者となります。
たとえば、紙幣や硬貨には代替性があり、替えが効きます。つまり、自分が持っている1万円札は他の人が持っている1万円札と全く同じ価値をもちます。一方で、人は唯一性や希少性のあるもの、つまり「替えが効かないもの」に価値を感じます。
不動産や宝石、絵画などPhysical(物理的)なものは、証明書や鑑定書によって「唯一無二であることの証明」ができます。しかし、画像や動画などのDigital(デジタル)な情報は、ディスプレイに表示されているデータ自体はただの信号に過ぎないため、誰でもコピーできてしまいます。
NFTではそれぞれのNFTに対して識別可能な様々な情報が記録されています。そのため、そういったデジタル領域においても、本物と偽物を区別することができ、唯一性や希少性を担保できます。
つまり簡単にいうと、NFTとは、耐改ざん性に優れた「ブロックチェーン」をデータ基盤にして作成された、唯一無二のデジタルデータのことを指します。イメージとしては、デジタルコンテンツにユニークな価値を保証している「証明書」が付属しているようなものです。
NFTについては以下で詳しく解説しています。
ブロックチェーンゲーム

前述のNFTはファッションやチケットなど様々な分野で活用されていますが、なかでもゲーム分野ではその特徴が遺憾なく発揮されています。
NFTはデジタルデータの価値を保証できると説明しましたが、これをゲーム内コンテンツに転用することによって、ゲーム内での通貨やアイテムにも金銭的価値を生み出すことができます。
ブロックチェーンゲームにおいては、通常のキャラクターやアイテムがNFTで作成されています。そのため、ゲームを進めていくと入手できるレアなアイテムや育成したキャラクターを、ユーザー同士で売買することも可能です。
いままでも獲得した通貨や経験値でアイテムを購入することはできましたが、仮想通貨で他のユーザーとアイテム単位を売買することはできませんでした。その点、ブロックチェーンゲームではひとつのアイテムをほかのサービス会社で使用可能なこともあり、ゲーム内の収益をそのまま現実の収益とすることができます。
これを受けて最近流行しているのが「Play to Earn(遊んで稼ぐ)」という概念です。アクションやシューティングといったプレイスキルが求められるジャンルだけではなく、「学ぶ」「寝る」「食べる」「運転する」といった誰でも簡単にできるジャンルにも応用されているため、今後さらに市場規模が膨れ上がるのでは?と期待されています。
こうしたエンタメ業界はWeb3.0に適合しやすく、カードゲームや音楽といった業界なども続々とWeb3.0に参入しています。また、Web3.0関連銘柄への投資に特化したファンドも設立され、一部のエンタメ企業が注目しはじめています。
ブロックシェーンゲームiについては以下の記事で詳しく紹介しています。
DeFi
DeFiとは、「Decentralized Finance」の略で、日本語では「分散型金融」と訳されます。端的にいうと中央の管理者がいない金融システムのことを指します。
従来の金融システムでは銀行や証券会社といった中央集権的な管理者を経由してサービスを利用する必要がありました。しかし、DeFiでは仲介役となる中央管理者を介さずに、ユーザー同士で金融サービスを利用できます。
したがって、中央管理者を介しての取引で発生していた無駄な手数料や承認までのラグといった金銭的・時間的コストを大幅に削減できるというわけです。
また、「ウォレット」と呼ばれる仮想通貨を管理する財布のような機能を持ったツールさえあれば、場所や時間を問わずに世界中の様々なDeFiサービスも利用できます。「会員登録」や「審査」といった口座開設に伴う面倒な手続きも必要ありません。
一つのウォレットで世界中のサービスが利用できるということは、今までのように資金を移動する際にわざわざ両替をしたりアカウントを使い分けたりする必要がなくなるということです。自分のウォレットを接続するだけであらゆるサービスを利用することができるため、国籍や年齢、性別などに関係なく、全てのユーザーが平等に利用できるのです。
世界中の金融サービスをシームレスに体験することができる画期的な仕組みであるDeFiも、管理者不要でデータの安全性が担保されるWeb3.0ならではのアイデアだといえるでしょう。
DeFiについては以下の記事で詳しく紹介しています。
DAO
DAO(ダオ)は「Decentralized Autonomous Organization」の略で、日本語では「分散型自律組織」と訳される、ブロックチェーン上で管理・運営される組織のことです。
株式会社などの一般的な組織とは異なり組織の管理者が存在しないという点が、DAOの大きな特徴のひとつです。組織の意思決定は管理者によるトップダウンではなく、組織の参加者全員によって平等に行われます。
この平等性をもたらせているのが、事前に設定した特定の条件が満たされた場合に、決められた処理を自動で行う「スマートコントラクト」という機能やプラットフォームの意思決定プロセスに参加するための投票権を表現する「ガバナンストークン」という概念です。
こうした技術によって、透明性が高く公平な意思決定が可能になっています。身近なものを例に挙げると、「ビットコイン」もDAOです。ビットコインには特定の管理者がおらず、世界中のコンピューターによるマイニングによって、ブロックチェーンが管理されています。
このように、中央管理者がいなくても成り立つ組織構造が「DAO」であり、それぞれ独自のシステムを持ち、Web3.0の技術を活用して運用されています。
DAOについては以下の記事で詳しく紹介しています。
まとめ
本記事ではWeb3.0について解説しました。
WEB3.0は、WEB2.0時代の問題を解決するソリューションとして構想されています。私たちの生活や仕事に与える可能性があることから、今後ますます注目を集めることが予想されます。
Web3.0を過大評価することはできないとは述べたものの、巨大企業に個人情報が集中している現状からの脱却を図り、権力の集中を避けるという面では、既存のインターネットの構図を大きく変える可能性もあります。
引き続きWeb3.0の行方には目を光らせておかなければならないでしょう。
-1.png)