ブロックチェーンは、その世界市場規模が2030年までに4,694億9,000万ドルに成長すると予測されている有望技術です。とくに物流業界とは相性がよく、在庫管理や偽造品排除などさまざまな側面から注目を集めています。IBMなどが取り組んでいる事例と共に最新の物流DX動向に迫ります。
いま、「物流×ブロックチェーン」が熱い。
2025年現在、物流の一連の流れを最適化するという「ロジスティクス」とブロックチェーンを掛け合わせたビジネスが、世界的な盛り上がりを見せています。
今まで話題になることが多かったブロックチェーンの用途は、ビットコインなどの仮想通貨、NFTなどの独自トークンなどでしょう。しかし、近年ではサプライチェーンマネジメントの観点から国内外の企業においてブロックチェーンの導入が浸透しつつあります。
MarketsandMarkets社の発表したレポートによると、世界のサプライチェーンマネジメント (SCM) の市場規模は、2020年の約2億5300万ドルから2026年32億7200万ドルまで約53.2%のCAGR(年平均成長率)で成長すると予測されています。
このことからも近い将来、物流とブロックチェーンは切っても切れない関係になるでしょう。では、ブロックチェーンが実現するサプライチェーンマネジメントとは一体なんなのか、そもそもブロックチェーンとはどういう技術なのかについて軽くおさらいしましょう。
ブロックチェーンとは?
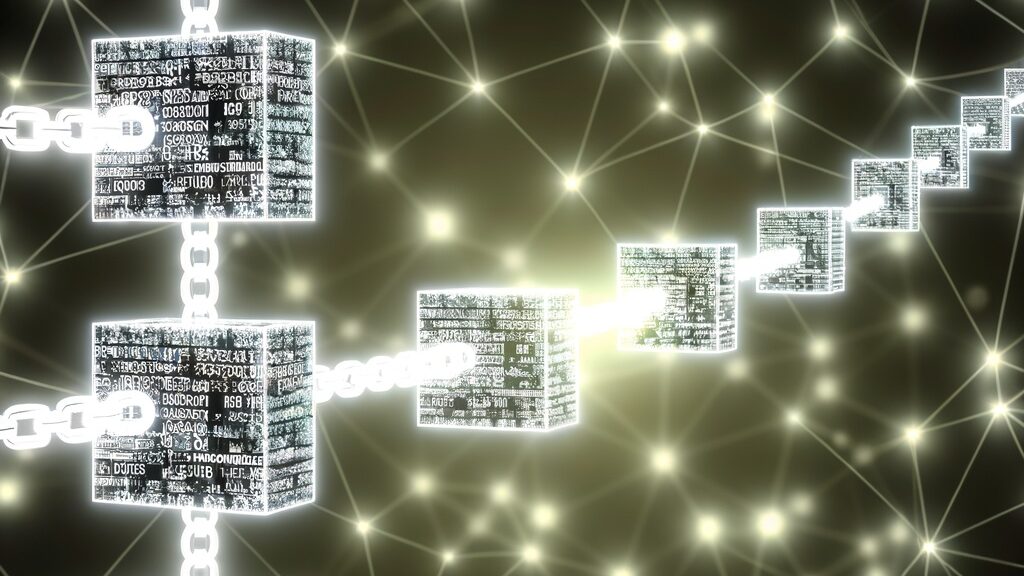
ブロックチェーンは、2008年にサトシ・ナカモトと呼ばれる謎の人物によって提唱された暗号資産「ビットコイン」の中核技術として誕生しました。
ブロックチェーンの定義には様々なものがありますが、噛み砕いていうと「取引データを暗号技術によってブロックという単位でまとめ、それらを1本の鎖のようにつなげることで正確な取引履歴を維持しようとする技術のこと」です。
取引データを集積・保管し、必要に応じて取り出せるようなシステムのことを一般に「データベース」といいますが、ブロックチェーンはそんなデータベースの一種です。その中でもとくにデータ管理手法に関する新しい形式やルールをもった技術となっています。
ブロックチェーンにおけるデータの保存・管理方法は、従来のデータベースとは大きく異なります。これまでの中央集権的なデータベースでは、全てのデータが中央のサーバーに保存される構造を持っていました。したがって、サーバー障害や通信障害によるサービス停止に弱く、ハッキングにあった場合に、大量のデータ流出やデータの整合性がとれなくなる可能性があります。
これに対し、ブロックチェーンは各ノード(ネットワークに参加するデバイスやコンピュータ)がデータのコピーを持ち、分散して保存します。そのため、サーバー障害が起こりにくく、通信障害が発生したとしても正常に稼働しているノードだけでトランザクション(取引)が進むので、システム全体が停止することがありません。
また、データを管理している特定の機関が存在せず、権限が一箇所に集中していないので、ハッキングする場合には分散されたすべてのノードのデータにアクセスしなければいけません。そのため、外部からのハッキングに強いシステムといえます。
ブロックチェーンでは分散管理の他にも、ハッシュ値やナンスと呼ばれる関数によっても高いセキュリティ性能を実現しています。
ハッシュ値は、ハッシュ関数というアルゴリズムによって元のデータから求められる、一方向にしか変換できない不規則な文字列です。あるデータを何度ハッシュ化しても同じハッシュ値しか得られず、少しでもデータが変われば、それまでにあった値とは異なるハッシュ値が生成されるようになっています。
新しいブロックを生成する際には必ず前のブロックのハッシュ値が記録されるため、誰かが改ざんを試みてハッシュ値が変わると、それ以降のブロックのハッシュ値も再計算して辻褄を合わせる必要があります。その再計算の最中も新しいブロックはどんどん追加されていくため、データを書き換えたり削除するのには、強力なマシンパワーやそれを支える電力が必要となり、現実的にはとても難しい仕組みとなっています。
また、ナンスは「number used once」の略で、特定のハッシュ値を生成するために使われる使い捨ての数値です。ブロックチェーンでは使い捨ての32ビットのナンス値に応じて、後続するブロックで使用するハッシュ値が変化します。コンピュータを使ってハッシュ関数にランダムなナンスを代入する計算を繰り返し、ある特定の条件を満たす正しいナンスを見つけ出す行為を「マイニング」といい、最初にマイニングを成功させた人に新しいブロックを追加する権利が与えられます。
ブロックチェーンではマイニングなどを通じてノード間で取引情報をチェックして承認するメカニズム(コンセンサスアルゴリズム)を持つことで、データベースのような管理者を介在せずに、データが共有できる仕組みを構築しています。参加者の立場がフラット(=非中央集権型)であるため、ブロックチェーンは別名「分散型台帳」とも呼ばれています。
こうしたブロックチェーンの「非中央集権性」によって、データの不正な書き換えや災害によるサーバーダウンなどに対する耐性が高く、安価なシステム利用コストやビザンチン耐性(欠陥のあるコンピュータがネットワーク上に一定数存在していてもシステム全体が正常に動き続ける)といったメリットが実現しています。
データの安全性や安価なコストは、様々な分野でブロックチェーンが注目・活用されている理由だといえるでしょう。
詳しくは以下の記事でも解説しています。
現代ビジネスに欠かせないサプライチェーンマネジメントとは?
サプライチェーンマネジメント=生産フローの最適化
サプライチェーンマネジメントとは、その名のとおり、原材料の調達から製造、販売までの生産プロセス(サプライチェーン)を管理することです。在庫管理、出荷などの各段階でデータを取得・共有することで、各工程における無駄を省き、従来埋もれていたデータを有効活用することで、新たなビジネス戦略を構築することも可能になります。
サプライチェーンマネジメントの実現によって、具体的には以下のようなメリットが得られるでしょう。
- 配送や出荷における時間や労力の無駄を減らせる
- 原材料を必要な分だけ調達できるようになる
- プロセス全体を可視化し、透明性を高めることができる
- 自動認証により人的ミスを排除できる
- 温度管理が必要な商品を最適に管理・配送できる
- 機械的に在庫要件を予測できる
なぜサプライチェーンを管理する必要があるの?
現代のマーケットではネット上で商品の取引が行われ、消費者のもとに届くまでに複数の業者が携わることが一般的になっています。生産すれば生産した分だけ売れるという時代は過去の話となり、必要な商品を必要なだけ生産することが重要です。そんな多くのモノであふれる時代においてグローバルな競争に打ち勝つためには、サプライチェーン全体でリソースや情報を共有し、欠品や過剰在庫を回避する必要があります。
また、消費者がインターネットやモバイルで商品を見つけると、いますぐに入手したいと考えるでしょう。この消費者のニーズに応えるには、常に在庫を確保し、スピーディーな配送環境を整える必要があります。一方で、企業や部門ごとに独自に生産量や在庫を管理してしまうと、余剰在庫が発生して機会損失が増加する可能性があります。したがって、ユーザーの要望に合わせた効率的な生産と供給を実現するためには、サプライチェーンの管理が必要不可欠なのです。
ブロックチェーンと物流課題の相性の良さ
ブロックチェーン技術の特徴である「非中央集権性」や、サプライチェーンを取り巻く現状を踏まえると、なぜ今「物流×ブロックチェーン」が注目されているのでしょうか。その理由を一言でいえば、「物流業界のニーズとブロックチェーン開発会社のシーズが見事に一致したから」と言えるでしょう。
物流業界のニーズ
物流業界には長年解決されていない課題が存在していました。特に、「業界全体の取引をデジタル化しようにも、プレーヤーが多すぎて中央のデータベースを管理する主体が決まらない」という点が大きな障害となっていました。各企業が独自に情報を管理し、共有することが難しいため、効率的な取引が阻まれていたのです。
これに対し、ブロックチェーンは「非中央集権性」を特徴としており、中央の管理者がいなくてもシステム全体が安全に運営できる仕組みを提供します。具体的には、取引データの共有が透明で改ざん不可能な形で行われ、複数のプレーヤーが協力し合うことで利害の衝突を避けながら、より効率的に情報を交換できます。物流業界が抱えていた課題を解決するために、まさに最適な技術がブロックチェーンだったのです。
ブロックチェーン開発会社のシーズ
一方、ブロックチェーンの開発会社にとっては、技術的な進展が金融分野を超えてさまざまな領域に応用可能であることが明らかになり、次なるビジネス機会を求めていました。特に、暗号資産(仮想通貨)に依存しない新たな適用領域を模索していたのです。開発会社がシーズとして注目した条件は、以下の通りです。
- データベース共有によるコスト削減メリット:物流業界はプレーヤーが多いため、非効率的な取引が行われており、ブロックチェーンによるコスト削減の可能性が大きい。
- 非中央集権性:中央の管理者が不在でもシステムが円滑に機能する環境が求められるため、「GAFAのような中央集権的な存在がいない」業界が理想的。
- 優れたトレーサビリティ(データの追跡可能性):物流業界にはしばしば情報の不正確さや不透明さが問題となっており、ブロックチェーンの優れたトレーサビリティ機能が重要視されていました。
これらの条件に合致する業界として、まず不動産や医療分野が注目されました。不動産業界では、物件の所有権や取引履歴の管理が複雑で、中央集権的な管理が必要です。ブロックチェーンを利用することで、物件情報を透明かつ安全に管理でき、取引の効率化とコスト削減を実現します。医療分野でも、患者情報や治療履歴の管理の透明化が求められ、ブロックチェーンによる情報共有が診療の質向上とコスト削減に寄与することが期待されています。
特定の業界でブロックチェーンのビジネス導入が進むと、今度はより多くのプレイヤーが絡むサプライチェーンの透明化へとその舞台を移し、物流業界は適用領域の一つとして検討が進みました。物流業界では、複数の企業が関与するため、取引の透明性や追跡可能性が重要です。ブロックチェーン技術を導入することで、商品の流れや品質、運送状況などの情報を一元的に管理でき、取引の信頼性を高めるとともに、サプライチェーン全体のコスト削減が実現可能となります。
このように、複数のプレイヤーが関わる物流業界は、データ共有やトレーサビリティの向上、コスト削減が求められており、ブロックチェーンの特性がそのニーズにうまく応える形で注目されているのです。
物流におけるブロックチェーンの適用シーン
ここまではブロックチェーンとサプライチェーンマネジメントの概要について見てきました。サプライチェーンマネジメントはブロックチェーンがなくとも実現できる概念ですが、ブロックチェーンを導入することで可能になることも数多くあります。ここからは、ブロックチェーンによるサプライチェーンの管理についてご紹介します。
在庫管理

前述のようにブロックチェーンは、取引の正当性を中央サーバーではなく、ネットワークの全参加者が共有情報として扱います。そのため、データの改ざんが非常に困難であるうえ、情報の迅速な共有と作業効率化が可能です。
従来の在庫管理では、それぞれの企業が独自のデータベースでストック管理をしていたため、企業間の情報共有に時間的な問題や、正確性の問題がつきものでした。
ブロックチェーンを用いた在庫管理では、QRコードやICタグ(RFID)とリーダーを使って位置情報をリアルタイムで記録します。これにより、在庫情報が正確に把握でき、大規模な棚卸作業が不要になります。
ネットワークの参加者全員で情報を共有するため、情報の共有に伴う煩雑な事務作業が不要になります。メールやチャットを介することなく、プラットフォーム上でスムーズに情報を得られ、多くの業務が効率化するでしょう。
実際に、ウォルマート、ネスレ、ユニリーバなどの有名企業では、在庫の追跡にブロックチェーンを自社のビジネスに導入しています。
国際配送

国際配送業界の情報システムは、デジタル社会となったいま現在も書類ベースで作業を行っています。参照する電子データもリアルタイムに更新されるものではなく、数十年前のEDI(インターネットや電話回線を通じたデータ交換)が現役で使用されているのです。
こういった状況から、国をまたいだ関係各社同士での連携においては、絶えずオペレーションエラーのリスクを抱えながら、ヒトによる非効率な突合作業が繰り返されることで、必要以上の膨大なコストがかかってしまっています。さらに、国際荷物の配送には原産地証明書が必要になるケースや、現地配送業者による不正行為などが問題になっており、この傾向は産業のグローバル化に伴ってますます顕著になっています。
こういった現象を踏まえて、現在の物流プロセスを簡素化しながら各商品を追跡できるというブロックチェーンの利点を生かしている企業もあります。バラバラに行われていた国際配送を一元管理することで、配達時間と不正行為を検出し、収益性・安全性の向上が見込めるのです。
決済

出典:Pixabay
ブロックチェーンは、セキュリティと透明性を確保しながら、国境を越えた支払いを簡素化できます。この仕組みにはスマートコントラクトという技術が用いられています。スマートコントラクトは、契約の条件を自動的に強制する自動実行契約です。買い手と売り手の双方の取引条件が満たされた場合にのみ、自動的に支払いが行われるように指定できます。
このスマートコントラクトの仕組みは自動販売機を例に説明されることが多いです。自動販売機では、顧客がお金を投入し、商品を選択すると、条件(投入額が商品の価格を上回る)が満たされた場合、自動的に契約が成立し、商品が提供されます。逆に条件が満たされていない場合、契約は成立せず、商品は提供されません。
このように、特定の条件をプログラムに組み込んでおき、それが満たされ際に契約が自動的に実行される仕組みを活用することで、特定のプロセスを自動化して仲介業者のコストを排除することが可能になるでしょう。
米国のペイメント事業大手Visa は、ブロックチェーンとスマートコントラクトに基づいて、請求と支払いの管理に役立つ独自の決済サービスを展開しています。
偽造品排除

偽造品は物流業界にとって最大の脅威の一つであり、ICC(国際商業会議所)およびINTA(国際商標協会)の報告によると、偽造品が世界経済に与える損失は令和4年には4兆6,800億ドル(約515兆円)に達するともいわれています。これは驚異的な額であり、偽造品問題がいかに深刻で広範囲にわたるものであるかを物語っています。しかしながら、これまで偽造品問題が解決できなかった理由は、既存の物流システムが「トレーサビリティ」、すなわち商品の追跡可能性を完全に高めることができなかったためです。
物流業界では、商品がどのように、そして誰が関与したのかを正確に追跡することが極めて重要です。従来のシステムでは、商品に関する情報が複数のステークホルダー間で分散しており、その透明性と正確性が欠如していました。そのため、偽造品が正規品として流通しやすく、取り締まりが非常に困難でした。
しかし、ブロックチェーン技術はこの課題に対して画期的な解決策を提供します。ブロックチェーンは、全ての取引データを時系列順に格納し、改ざん不可能な形で保存することができます。これにより、商品の履歴や取引経路が透明化され、「いつ」「どこで」「誰が」関与したのかが正確に把握できるようになります。分散型のデータ管理システムにより、情報は一元管理されることなく複数のノードに分散され、信頼性とセキュリティが強化されます。
このように、ブロックチェーン技術を活用することで、物流業界におけるトレーサビリティが飛躍的に向上し、商品の真贋を確実に確認できるようになります。これにより、偽造品が市場に流通するリスクを大幅に低減させることができ、消費者や企業の信頼を回復するだけでなく、物流業界全体の効率化と透明性向上にもつながります。偽造品問題への効果的な対策として、ブロックチェーンは今後、物流業界における重要な技術となるでしょう。
物流業界におけるブロックチェーンの活用事例
日本IBM×HBC
日本IBMは、2023年4月から医薬品データプラットフォームの運用検証を開始しています。このプラットフォームはブロックチェーン技術を使用して、医薬品の流通経路と在庫を可視化するためのもので、製薬企業、医療機関、医薬品物流企業などが参加します。プラットフォームはHyperledger Fabricというブロックチェーン基盤を使用し、医薬品の品質保持と偽造品の防止を強化しています。
このプロジェクトは、主要製薬企業も加入するコンソーシアム「ヘルスケア・ブロックチェーン・コラボレーション(HBC)」において検討されてきたもので、参加企業はプラットフォーム上で医療機関の在庫情報を管理し、品質管理や事業継続計画に関する情報を共有します。これにより、医薬品の安全性とトレーサビリティーが向上することを目指しています。
医薬品のトレーサビリティーは、品質保持や偽造品の防止などの観点から重要であり、欧米では既に法制化されています。たとえばアメリカでは、2000年代から州単位で医薬品のトレーサビリティに関する法律が制定されていました。これを全国基準にして、州を越えた医薬品のトレーサビリティを確立しようというのが、2013年制定の「医薬品サプライチェーン安全保障法」です。
日本では、国家レベルでトレーサビリティの実現に取り組まれているのは牛と米の食品トレーサビリティです。これらが法制化されたのは2000年代初頭に起きたBSE(狂牛病)問題と2008年に起きた事故米(汚染米)不正転売問題という事件が表層化したことがきっかけです。
責任追及の観点から受動的な動きによって制定された背景からもわかるように、日本では国家レベルで産業へ厳しい規制をかけるのをためらう風潮があるため、こうした分野では民間企業による主導が効果的かもしれません。日本の医薬品の安全性と相互運用性を世界基準に引き上げるうえで、今後も注目せずにはいられないプロジェクトです。
日本通運
「偽造品排除」の文脈でうまくビジネス利用しようとしているのが、日通(日本通運)です。
2020年3月9日の日本経済新聞の記事によると、「日本通運はアクセンチュアやインテル日本法人と組み、ブロックチェーン(分散型台帳)を活用した輸送網の整備に乗り出」し、「倉庫の整備などを含め最大1千億円を投資する」ことで、「偽造医薬品の混入を防ぐための品質管理に生かし、将来は消費財全般に応用する」ことを発表しています(「」内は同記事からの引用)。
上図のように、ブロックチェーンを利用した偽装品排除の取り組みでは、メーカーから小売に至るまで、川上から川下のデータを同一クラウドデータベース上にすべて紐づけていくことで、ある商品がいつ、どこで、誰によって、どんな状態で管理されているかを可視化することができるようになります。
これにより、商品のトレーサビリティが高まり、産地やハラールの認証、違法コピーなど様々な偽造品問題を解消できるのではないか、と期待されています。
トレードワルツ
国際物流におけるブロックチェーン導入の代表例ともいえるのが株式会社トレードワルツ(本社:東京都千代田区、代表取締役社長:小島 裕久)の「TradeWaltz」です。同サービスはブロックチェーンを基盤に、貿易手続きの完全電子化を目指す貿易情報連携プラットフォームです。
現在の国際物流システムにおいて、荷主、保険会社、物流会社、税関といった貿易の関係者は各社で独自のシステムを持っていますが、これらのシステムとデータは相互に連携できていないケースがあります。そうした場合、煩雑な書類手続きが必要で、紙ベースで送受信された情報を各社が手動で転記しなければいけません。書類エラーにより手戻りも頻発します。
このような貿易取引の課題を解決するのが、貿易情報連携プラットフォームTradeWaltzです。
TradeWaltzでは、各企業のシステムと接続することで、関連書類の電子的な送受信と保管をアプリ上で行うことができ、業務の効率化を図っています。情報の正確性に関しては、ブロックチェーン技術を用いてドキュメントの原本を保証して改ざんを防ぐため、データを安全かつ信頼性の高いものとして扱うことができます。
日本と世界のアナログな貿易手続きの完全電子化・業務効率化を実現するこのソリューションは、名だたる企業からの注目を集めています。2020年11月に事業を開始すると、NTTデータや三菱商事、丸紅といった大企業から資金を調達しており、2023年5月には新たに住友商事が出資に加わり、累計の資金調達額が56.5億円に達しました。
トレードワルツが16.5億円を追加調達、累計56.5億円に──住友商事が新たに参画 | CoinDesk JAPAN
タイ、シンガポール、オーストラリア、ニュージーランドが持つ4カ国の貿易プラットフォームと、同時にブロックチェーン上でAPI接続する世界初の取り組みに成功し、今後は日本・インド太平洋地域間の貿易DXを推進するとのこと。「ブロックチェーン×物流」のリーダー的存在として活躍の場を大きく広げています。
まとめ
この記事では物流業界におけるサプライチェーンマネジメントの重要性と、ブロックチェーンの導入について詳しく見てきました。
実際の事例からも、多数のステークホルダーが存在し、サプライチェーンが複雑化する現代の物流システムでは、ブロックチェーンのような安全かつ分散的な技術が大きな期待を背負っていることがわかります。
ブロックチェーンを在庫管理などに活用することで、正確な在庫情報の確保や情報の共有がスムーズになり、効率化が図れます。しかし、導入には技術的な課題やセキュリティの懸念などもあるため、慎重な計画と実装が必要です。将来のブロックチェーン化に備えるためにも、一度自社のビジネスを見直してみてはいかがでしょうか。
トレードログ株式会社は、ブロックチェーン開発のエキスパートです。食品業界や製造業、物流業界などさまざまな業界に精通し、一社一社のビジネスモデルに最適化されたブロックチェーン開発を行います。
少しでも自社ビジネスに課題をお持ちでしたらぜひトレードログ株式会社にご相談ください。貴社に最適なソリューションをご提案いたします。
-1.png)
